Q & A 3
自然の教えをそのままに・・・
相手(自然=神様)の気持ちになって
1. 気候と生産性?(痩せの大食い>小食肥満)
一般的に熱帯・亜熱帯雨林の土壌は高温多雨で、有機物の分解が早く堆積物が少量で、養分流失も激しいため土は痩せています。痩せてはいますが、微生物や植物の活動は活発で、炭素(養分)循環速度が早く、絶対量は大きいため、バイオマスの生産性は高くなります。そして、少量の堆積物しかないため、一部の自然農法で行われるような、里山の落ち葉や下草利用はできません。逆に寒帯・亜寒帯(寒冷地、高冷地)は、微生物や植物の活動に適した期間が短く、養分循環速度が遅いため、バイオマスの生産性は低くなります。しかし有機物の分解が遅く、分厚く積もった堆積物があり、土(堆積物を含めた)の養分蓄積量が大きく肥えています。
このような肥沃化しやすい地域では、肥沃度のコントロール(里山の利用)をしないと、本来は痩せ地の植物である松などが枯れたり、萱・葦原などが消滅します。
里山の利用: 適度な有機物の持ち出しや野焼きをしないと肥沃度が上がり、肥沃な土地を好む植物へと植生が変化する。松枯れは放置・肥沃化による植生変化の自然現象であり、センチュウや松くい虫は結果、原因ではない。彼らは環境変化に適応できず、弱った松を処分している。
有機物の持ち出し可能な量は地域差が大きく、里山に依存する農法は自然農法の基本的技法とは言い難い。
有機物の持ち出し可能な量は地域差が大きく、里山に依存する農法は自然農法の基本的技法とは言い難い。
つまり自然状態の土壌では生産性の高い土ほど痩せ、低いほど肥えているのです。生産性は気温(地温)や有機物の分解(循環)速度に正比例し、土壌の肥沃(蓄積)度には反比例するという関係です。
そして、微生物や植物による炭素や窒素の養分固定(捕捉)力は土壌の肥沃度が低いほど高く、肥沃度が高いほど低いと言えます。
日本のクヌギや杉は10cm径以上になるまでに15年前後。ここ(南回帰線上・標高800m)に移入されたものは年輪幅が1〜3cm。1/5〜1/2の期間で同じ径になる。材の緻密度を加味しても平均で3倍ほどの性産生(循環度)と考えられる。
|
■ ■低■■■肥沃度■■■高■ ■
高 ■高■■■生産性■■■低■ 低 温 ■高■■■捕捉力■■■低■ 温 ■ ■高■■■循環度■■■低■ ■ |
この仕組みを農業の現場で応用するのには、熱帯では雑草や緑肥作物などで大量の有機物を確保し養分をできるだけ逃がさないように土と混ぜ、表面は草生マルチなどで保護します。
寒帯・亜寒帯では作物の生育に必要な養分量は、土壌中の作物残滓程度で間に合います。しかし、低温で単位期間当たりの有機物分解量が少ないため、有機物マルチなどで保温や乾燥防止、雑草抑制を兼ねて必要量の有機物を確保すれば良いわけです。
これで両者とも自然林野と、ほぼ同じような土壌環境になります。しかし、見た目の模倣ではなく、循環量・速度の状態のことです。近くの手入れしていない雑木林の状態がお手本。
表現を変えると、熱帯土壌は炭素量に敏感に反応しダイエット(土壌の浄化)が容易。寒帯・亜寒帯では鈍感で困難です。熱帯の土壌は痩せの大食い、寒帯・亜寒帯は小食肥満タイプ。
一部の自然農法では、作物残滓や雑草、作った緑肥作物などを圃場外に持ち出します。これは慣行農法と全く同じ発想(防除)の「殺し行為」です。実際にこれを行うと炭素(微生物の餌)不足から浄化が進まなくなります。
肥満状態の場合なら、土を痩せさせれば、植物が養分を求め根圏が拡大するため、全体での養分固定(捕捉)力は高くなり循環度が上がります。でも過ぎれば「水清くして魚棲まず」微生物の多様性を損ない免疫力低下を招きます。
2. 浄化度?(害虫同様に害物?は幻)
無施肥による自然農法を長年続け、過度の浄化が行われると、現代人のように衛生状態が良くなり過ぎて、免疫を獲得する機会が減りアレルギー疾患などが増えるのと同様、土でも似たような現象が起きます。これは、その土地に生えた雑草や作物残滓まで取り除くような極端な浄化を行った場合です。土は生きています。土の腸内細菌とも言える、土壌中の微生物叢(相)が過度の有機物制限により、単純化・弱体化し適応力を失った結果です。
作物に対する養分供給力は十分でも、多様な経路から入ってくる、農薬(周囲での散布、種子消毒など)や環境汚染物質が、微量ではあっても分解されず作物に残留し、化学物質過敏症の患者は反応します。
自然(陸・海・空)は殆どのものを分解します。セルロースやリグニンなどの分解屋、キノコ菌がダイオキシンを分解することからも分かるように、陸の腸(土)にも繊維質が必要なのです。順序から言えば人は自然を裏返しにし、内側に土壌を持ち歩いているという説の方が妥当。人に繊維質が必要なのは当然と言えるでしょう。
土のアレルギー、過敏症といったところです。これを防ぐ有機物量の目安は、自然の循環から考えて、その土地でできる物(緑肥を含め)から収穫分を除いた残りの全てと思えば良いでしょう。実際の量は、気候の違いで数倍の差が生じます。
また、残滓が少ない作物や、欲張る場合は(^-^)周囲の環境の許す範囲内で、多少の持込も考慮する必要があります。
炭素循環農法では、せっかくできた雑草や作物残滓を持ち出すなどという勿体ないことは考えません。持ち出さなくても、逆にそれを活用する土壌浄化法が分かっているからです。要は土自体を痩せさせ、同時に養分バランスを整えることができればよいのです。土でも人でもバランスの崩れは病気の元です。
病害虫に対する防除という概念を捨てると同時に、自然環境中に普通に存在する全ての物(人工的化学物質は別)に対しても、害虫と同様に害物?は幻と捉え、それを排除するという考えは捨てなければなりません。
物事を善悪で判断した結果が、悪いものは取り除くという既成概念です。共生(全てを生かす)の意味を理解すれば、取り除くなどという発想は起きないはずです。取り除けば、その先での処理が待っています。原則は自己処理です。
3. 善悪?(流れの方向と順序)
微生物や虫を増やすと有用菌(虫)だけではなく害菌(虫)や無用菌(虫)?も増えるのでは?、との懸念は無用です。そもそも善悪と言われているものは相対的な問題で、絶対的なものではありません。場の状態(環境や宿主の健康状態等)次第で善にも悪にもなります。また、何れか一方が増えれば他方は減ります。どちらが増えるかはその場の環境次第で、善が増えれば悪は悪ではなくなり、悪が増えれば善が善の作用を失います。これは普段どっち付かずの日和見菌(虫)が優勢になった方に加勢し、今まで善や悪だったものが日和見的になるからです。日和見的性質は程度の差はあっても、全ての菌が持っています。
| 有用菌、益虫 ■善■■■■ 日和見 ■■■■悪■ 害虫、有害菌 |
この際、環境整備にEM菌などの微生物製剤や土着菌、米糠などの起爆剤が役立ちます。しかし整備が終われば必要ありません。既にキノコ菌が有機物を占有している廃菌床を使った場合や、土がある程度できれば微生物製剤や米糠も必要なくなります。
また○○菌が良いとよく言われますが人工的な廃棄物処理などは別として、一般的土壌では場の調整(環境整備)が大切で特定の菌が必要ということはありません。多様な微生物製剤がありながら安定した効果が得られないのはそのためです。そして、どのような資材でも有限ですから、原則はあくまでも圃場内での自給自足です。
一般的には生の緑肥を鋤き込むと、ピシウム菌やフザリウム菌等の有害菌が繁殖するからいけないと言われます。また、他の糸状菌も多くは病原性を持つと言われています。しかしそれ等も適正な炭素比にして有用作用のあるキノコ菌等を先に働かせれば何の問題も起きません。
しかしキノコ菌が有用だからといって、他の菌類(カビ)や細菌類(バクテリア)が無用だということではありません。場の調整には全てが必要であり、本来は全てが有用(善玉)なのです。何事にも流れの方向と順序があり、これさえ間違えなければ良いのです。単純化すれば、有機物→菌類→細菌類→無機物→有機物→菌類→・・・、となります。
溜まり水が腐敗することを見れば解るように、害作用とは、このような流れが滞るとき現れる現象です。特に菌類を飛び越し細菌類が作用すると、無理が生じ窒素の滞り(無機態窒素の蓄積)が起き、土壌物理性が劣悪化、植物にとって生育環境が不適になり、結果として虫や菌を呼びます。
4. 手抜き?(自然はフラクタル)
|
77777777 77555577 75777757 77777577 77775777 77757777 77577777 75555557 77777777 |
77777777 77555577 75777757 77777577 77775777 77757777 77577777 75555557 77777777 |
本来の知覚以外の感覚が同時に働く現象を共感覚と呼びます。数と色には絶対的な対応関係があり、共感覚者は数の性質(本質)を色感で捉えているのです。
共感覚: 食べものに味覚と同時に形を感じる。音や文字から色が見える。目で見ただけで触感を感じる。等々「一つの感覚の刺激によって別の知覚が不随意的に引き起こされる(リチャード・E・シトーウィック)」知覚現象。
これは形も性質も違う非自己相似の入れ子の例です。しかし白黒では分かり難いですね。図の右のように見えれば便利なのですが誰でもというわけにはいきません。7に2が、2に5が入れ子になっていて、7や2とみても5の集団とみても、間違いとは言えませんが正解とも言えません。
事象を分析的に個々に捉え「これは・・・である」というだけでは正解と言えないのが自然(生命現象)の厄介なところ(分析的実証法の限界)です。
でもこのような仕組み(入れ子構造)があることが分かれば、何処をどのようにすれば良いかが見えてきます。自然は似たような構造(仕組み)が入れ子になっていて、それは物の形だけではなく、物質循環や免疫機能などのような仕組みも同様です。
ですから、一つの階層での仕組みが分かれば、下や上の別の階層でも同じような仕組みということが分かります。
そして一番内側の入れ子から整えれば全体が整うということが理解できます。生命体の最小単位である微生物(細胞)から生かせば、上位(自然は階層構造)の人が生きられるという、原理的には非常に単純な仕組みです。
人が余計な手を出さないというのが手抜き農法の意味ですが、何でも同じような仕組み(自己相似)を入れ子にする神様の究極の手抜き^-^の応用という意味でもあります。手抜き・自然農法=フラクタル農法です。
フラクタル: 幾何学の概念。図形の部分と全体が自己相似になっているもの(数学者ブノワ・マンデルブロが導入)。自然科学の新たな解明手法。フラクタル図形は自然界のあらゆるところにみられる(海岸線や樹木の枝分かれなど)。
腐敗現象の入れ子を考えてみます。人(全体)が炎症(腐敗)を起こさないためには、食物(部分)を腐敗しにくくすれば良いのです。食物(全体)を腐敗させないためには、作物が育つ土(部分)を腐敗から守れば良いのです。土(全体)を腐敗させないために、腐敗・分解作用を起こさない微生物(部分)を育てれば良いのです。その微生物(全体)を育てるために、高炭素の腐敗しにくい餌(部分)を与えるというわけです。
逆に上の階層をみれば、人(部分)の腐敗が地域や国家(全体)を、地域や国家(部分)の腐敗が地球(全体)を腐敗させます。
人は精神的な生き物ですから精神的・社会的な面で行動が規制されます。精神論では作物は育ちませんが、心の腐敗の結果による行動が地球の物理的環境破壊を招くことは確かです。
自然が入れ子・階層構造なのですから、単独では何者も生きることはできず「共生」が当然であり農業も例外ではありません。
有機的な繋がりを無視しては持続可能な農業は成り立たず、真の有機農業以外に農業者が、そして人々が生きられる道理がない理由がここ(フラクタル構造)にあるわけです。
5. 機械農?(虫を手で取りゃ・・・)
施肥・殺し信仰は有機・自然農法にまで根深く浸透しています。その反面、有機・自然農法の支持者は何でも自然のままが良いだろうとの考えに陥りがちです。その典型が、不耕起、大型機械排除、天然資材なら何でも良いなどです。これは逆恨み的な(笑)、過剰反応であり「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の類です。単に自然の猿真似、自然信仰と言ってよいでしょう。
有機堆肥を使ったからといって有機農法にならないのと同様、格好だけ付ければ、自然農法になるわけではありません。耕すから土壌の劣化を招いたり、表土流亡が起こるわけではありません。大型機械を使うから土が固まり硬盤層ができるわけでもないのです。
ましてや、農薬を使わず虫を手で取りゃ良いってものではありません。防除は手段を問わず殺し行為であり、虫の餌を横取りすることに変わりないのです。全ての命を生かすことができない農法には、どこかに矛盾(反自然)があります。
過渡期では仕方がない現象なのかもしれませんが、自然を十分理解することなく安易な猿真似に走り「これが自然なんだ」というのは、信じ込んでいるだけに慣行農法より始末が悪いとも言えます。
一般の人々の自然農法に対する見方を歪めるだけではなく「そんな原始的農法では全世界の人々の食糧を確保できない」と一般に思わせ、皮肉なことに有機・自然農法の理解や普及を自ら妨げているからです。
自然の意思は命を生かすことです。自然は人に、より活き良く生きること以外、何一つ要求しません。そのために人が手を加えるのなら、自然に反するとは言えません。見た目や資材、手段に関係なく、自然並み(以上)の土壌環境や環境保全ができ、健康に良い美味しい作物を作れるなら、より自然の意思に沿うことになります。自然農法は自然信仰(崇拝)ではないのです。
趣味や道楽、自然信仰なら、それはそれで結構。他人の自己満足をとやかく言うつもりはありません。また、自然にできるだけ負荷をかけないような、ライフスタイルに見直すことも必要と思います。
でも、誰しもが自然の中で自給自足などの贅沢?ができるわけではありません。都市化は避けられないでしょうし、そこに暮らす不幸?な人々(笑)の食糧確保のための効率的、専業農業が必要です。
人は猿ではありません。より進化し高度な文明を持つ人類の地球規模的な自給自足を考えれば、大規模機械農業は必然です。これに対応し自然の意思に沿うことができなければ反自然農法なのです。
6. 無機・人工?(処分の対象にさえならなければ)
一般的には作物の養分コントロールを無機物で行う無機農法?に対して、有機物(堆肥)を使えば有機農法と漠然と思われているようです。ところが実際には両者とも無機養分による人為的コントロールで無機農法です。堆肥化は人工的な無機化の前工程で、作物は肥料で育つとの思い込みによる有機物の無機・肥料化です。しかし無機化が不完全なため、残った有機物が微生物の餌となり土壌が改良され、間違って?土が良くなってしまうのが有機堆肥農法なのです。
そもそも間違いが出発点ですから一生懸命やればやるほど、おかしくなるのは当たり前です。
人が何を与え何をしようと、植物が何(有機物、無機物)を利用しようと、人が養分を直接コントロールせず有機体(生物)に任せ、間接的にコントロールするのが有機・自然農法です。間接的であれ人為的コントロールがなければ農法とは言えません。
養分コントロールを任せた以上、当然、その結果についても責任を取ってもらいます^-^。それが虫(菌)による活きの悪い作物の処分(病虫害)です。処分の邪魔をしてはいけないのは自明の理です。
自然は、ヒトに相応しい食物を与えようとしているのにもかかわらず、意地汚い?ヒトは、自然の思惑(仕組み)を無視し、毒を食らっているのです。神様は「もううんざり、やっちゃいられませんよ」とは言いません(笑)。しかし絶対にお目こぼしはしてくれません。自己や種族の保全、進化の邪魔になれば、自然状態の生物や農作物と同様に、ヒトも確実に処分の対象にされます。これは生物生存の原理です。
ですから、どんなに人工的であっても処分の対象にさえならなければ、それは自然の意思に合致していると言って良いわけです。途中経過は無防除・無隔離で虫(菌)に判断を仰ぎ、最終的には人が食べた結果をみて判断すれば良いのです。
「人の食物」の真の意味を理解し、現在の技術力をもってすれば、ハイポニカでも野菜・キノコ工場、卵・肉工場などでも実質的な自然農法(人が手を出すが処分は虫や菌まかせ)は可能と思います。
ただ現段階では殆どの場合、無農薬・無医薬でも、隔離という防除手段を講じていて、自然の意思に反した反自然・殺し農法です。人は道具を使い、自然にないものを作りだす能力を自然から与えられているのです。それを使うこと自体は自然であり、農業も例外ではありません。
勿論、物質循環が円滑に行われ、無公害で自然破壊・汚染のようなマイナス要因が伴ってはならないことは言うまでもありません。
7. 焼き畑?(慣行農法こそが略奪農業)
写真(左・上部)は30年間、人手が一度も入っていない雑木林です。南回帰線上、標高800m、実際に無施肥栽培が行われている圃場と同じ土です。写真(右)はその断面、落ち葉などの堆積物層は非常に薄く1〜3cm、腐植土層全体で10cm前後です。写真(左・下部)のように、傾斜地では連日の雷雨(夏)で薄い有機物層が流失し、地肌が露出、根がむき出しになっているところもあります。
 四季が温帯ほど明確ではなく、林全体では常緑状態です。落葉も年間を通してあり、有機物の分解が冬季でも行われるため、堆積量の通年変化は僅かです。土質は熱帯性の赤色ラトソルで、痩せた酸性土壌(pH5)です。
四季が温帯ほど明確ではなく、林全体では常緑状態です。落葉も年間を通してあり、有機物の分解が冬季でも行われるため、堆積量の通年変化は僅かです。土質は熱帯性の赤色ラトソルで、痩せた酸性土壌(pH5)です。地質的には農耕地として良いとは言えませんが、3〜5年ほどの周期で、1年間(2〜3回栽培)の短周期型の焼き畑(原始的・無施肥栽培)ができます。気候温暖、降雨量も十分(1400mm/年)で、雑草による炭素固定が盛んなためです。ただし、高温で有機物の分解が早いため、森林の再生期間を長くしたからといって耕作期間は長くなりません。(実際には自然林・再生林の伐採は法令で禁止されている)。
ラトソル(ラテライト性土壌): 母材は砂岩。超大陸以前の古い地質で、太陽熱・地下水・微生物等の作用で化学的風化を強く受け(成帯土壌)、アルカリ土類の金属イオン(Na,Ca,Mg,K等)が溶脱、痩せている。Fe,Alの水酸化物に富み濃い赤色を呈す。土壌浸食を受けやすい。赤道を中心に熱帯・亜熱帯地方に広く分布。ブラジルでも南部地方を除く、ほぼ全域を占め、代表的な農耕地土壌の一つ。
寒冷地では有機物の蓄積・分解が遅いため、10年〜数十年周期で耕作期間も長い(2〜数年)焼き畑が向いています。焼き畑の栽培周期は炭素の固定・蓄積量で決まります。
知識もなく、機械力もなかった時代では焼くのが最も手軽で簡単な方法です。農耕面積も森林面積に対し少なく、都市周辺を除けば焼き畑農業でも自然破壊を起こさない条件にあったわけです。
現在でも途上国では焼き畑がかなり行われています。人口増などで自給自足でも限界と思われますが、経済行為として原始的な焼き畑が許される、ゆとりは既にないでしょう。
でも、貴重な炭素資源を焼き払わずに鋤き込めば(場合によっては敷くだけでも)、同じ土地で連年栽培が可能になり、これ以上の森林破壊をしなくて済みます。
焼き畑は略奪農業と思われていますが自然の循環の範囲内で行われる限り、まことに合理的な農法なのです。自然状態での養分循環は、森林の炭素固定量に端的に現れ、森林が若いうちは固定・循環量が次第に増え、老齢化するとほぼ一定量を維持(二酸化炭素および酸素の吸収・排出が均衡)します。
適度な周期で焼いて森を若返らせれば、養分循環量は常に増える方向にあるため、増加分は人が持ち出しても養分収支は赤字(略奪)になりません。
持続的農業の原型(細切れ状態)が焼き畑であり、細切れを繋ぐことができれば永続的な土地使用が可能になります。炭素循環農法は、その理論と技術を体系化した焼き畑・改良版です。
耕作する以上、生態系の破壊は避けられません。尤も真の自然農法なら慣行農法のような壊滅的な破壊は避けられ、農耕地としての生態系ができ上がります。
炭素固定・循環はなにも、森林だけに限られたものではありません。農耕地でも森林以上の炭素循環は可能です。環境問題では炭素固定ばかり言われますが、それでは無意味です。特に農業では、如何に多くの炭素を固定し、その炭素を有効に放出するかが重要なのです。循環量が多ければ土壌の物理性が改善されます。
炭素の循環量に応じて、他の養分循環量が大きくなり、放出量や作物として持ち出す量も大きく(増収)なります。その分、肥料(化学肥料、堆肥)が少量あるいは不要になり、健全化した土壌は農薬を必要としません。全てのものが滞りなく循環することが重要なのであって、蓄積量は増えても減っても不健全です。
実は、現在の慣行農法こそが略奪農業です。炭素を土に還していないだけでなく、肥料製造のため新たな炭素を地下から略奪し、大気中に放出しています。有機(堆肥)農法にしても、他所から略奪した炭素資材を大気中で分解、炭素放出(堆肥化)をして、残りカスを土に還しているだけです。これでは対価を盗品で払う行為や、義賊の施しと同じでしょう。
現状のままでは地球の命を育むシステムそのものを略奪しかねない状況と言えます。そして慣行農法が略奪農法だと気付いているからこそ、永続的に持続可能な循環農法が模索されているのです。
8. 旬?(微生物が育てる作物を決めている)
作物を一度も作ったことがない新しい土は、有機物が十分有っても育たない作物があります。無施肥栽培では土に無機状態の養分が殆どありません。そのため作物と共生関係にある微生物が十分増えないと、作物への養分供給体勢が整わず生育不良になります。作物により共生・依存関係にある微生物が微妙に違いますから、作物自身が自分に合うように微生物を育てなければなりません。作物による土の教育と言えます。
土壌微生物に対する依存度は作物によって違い、マメ科作物は特に低く最初からよく育ちます。イネ科や根菜類なども比較的新しい土でも育ちます。イモ類などは中間で、葉野菜や果菜類は何回か他の作物を作ってからが良いと言われています。
この順序は肥沃度が低くても育つ(吸肥力が強く養分要求度が低い)ものから、高い肥沃度が要求される(吸肥力が弱く養分要求度が高い)ものへとなっています。肥沃な土とは単に養分の絶対量の問題ではなく、微生物相が豊かで養分供給体勢が整っている状態の土を指します。
微生物相は、四季の温度変化と共に常に変化し、高温時は高温に適応した作物に合う微生物相、低温時は低温に適応した作物に合う微生物相になります。微生物相が変化すれば、供給される養分のバランスも同時に微妙に変わり育てられる作物も変わります。
つまり、自然状態では微生物が育てる植物を決めていると言えます。微生物も植物も、それぞれの温度帯に適応しながら、同時に適応したもの同士が共生関係を持つように進化したためと考えられます。
慣行農法のように施肥で養分コントロールをしない無施肥栽培では、旬の作物を作ることが特に大切です。旬のものを作れば、気候が作物の生理特性に合うというだけではなく、微生物が作物に適合した養分供給を行い健康に育てます。また、逆に作物に合う微生物相を育てる管理(地温のコントロールなど)も農の技としては有効(必要)です。
旬のものがビタミンやミネラルが豊富で栄養価が高いのは、その作物にあった養分供給が微生物によって行われるためであったわけです。旬のものなら常に、その季節に必要なものを最良の状態で、人が摂取することができます。この旬という自然の合理性を無視し、季節外れの物を喜んで食べる消費者(特に日本人)が馬鹿だと言ってしまえばそれまでですが、それを供給するのは犯罪行為に等しいでしょう。
とは言っても旬を外すほど儲かるという現実の前に、農業者は無理をしてでも作り、その技術力を誇りとしています。消費者の皆さん、百姓を犯罪者にしないでください(笑)。農業者は高い技術力を人の健康のために活かしてください。
9. 循環量?(私ならこれだけですよ)
温帯から亜寒帯では有機物分解期間が比較的長く、必要炭素(有機物)量が少なくてすみ、肥沃度を考慮せず作物残滓程度で、清浄度だけ上げても作物が育つようになります。要するに土が鈍感。日本の無施肥の例では、必要量と言われる1/10以下の養分濃度でも作物が育っています。これは魔法ではなくトリック。2.23≒10。根が三次元方向に約倍、伸びれば良いだけ。
養分濃度は低くても最低限の養分量は確保でき、何の不思議もありません。ただ、横方向は隣と共有、根は縦に伸びる必要があり無施肥栽培は、心土でも作物を育てます。
熱帯では有機物に対する応答速度が速く非常に敏感。作物残滓程度では肥沃度が急速に落ちてしまい、清浄度も上げられず作物が育たなくなります。過度の浄化は「生かす」という目的に反します。
適正な有機物(炭素)量はその地方の、潜在自然植生による有機物純生産量の推定値が基準。これは「私ならこれだけですよ」と神様が手本として示した、最低限度の循環量と言えます。
それ以上でも構いませんが、以下では自然に逆らう行為。その結果が過敏症。この量はその土地の、緑肥作物(炭素固定量が最大になったイネ科)の生産量とほぼ同じ。循環量(作物分は除く)の目安です。
有機物分解期間: 熱帯雨林1年。温帯4年。亜寒帯30年。
潜在自然植生: 人為的影響を排除した時、その時点で成立しうるであろう最も発達した仮想の植生。(チュクセン 1956年)。
有機物純生産量: 有機物合成量から自己消費量を差し引いた正味量。
森林の有機物純生産量(ha/年/乾物): 熱帯雨林30〜40ton。温帯照葉樹林21ton ・温帯落葉広葉樹林9ton(平均的混交林15ton)。亜寒帯針葉樹林11ton。サバンナ4〜7ton。(炭素量なら50%)
緑肥作物(炭素固定量が最大になったイネ科)の生産量: 30t/ha/一作。
潜在自然植生: 人為的影響を排除した時、その時点で成立しうるであろう最も発達した仮想の植生。(チュクセン 1956年)。
有機物純生産量: 有機物合成量から自己消費量を差し引いた正味量。
森林の有機物純生産量(ha/年/乾物): 熱帯雨林30〜40ton。温帯照葉樹林21ton ・温帯落葉広葉樹林9ton(平均的混交林15ton)。亜寒帯針葉樹林11ton。サバンナ4〜7ton。(炭素量なら50%)
緑肥作物(炭素固定量が最大になったイネ科)の生産量: 30t/ha/一作。
分解率や貯留量を計算すると、寒冷地帯では分解量の少なさを貯留量で補うことによって必要な量を確保していることが分かります。貯留量が多くても余分にあるわけではありません。この神様の決めた基準量(推定量)は実際例とも良く一致し純生産量に差があっても、貯留量から取り崩される量はどの地帯でも10ton近くで同じです。
人為的に効率化している実際の畑では、倍ほどの生産性があると思われ収穫物を持ち出しても基準量を循環させれば、十分な量。更に土壌構造が出来上がれば作物残渣だけで十分です(場合によっては過剰)。
貯留未分解有機物の分解率(年): 熱帯100%。温帯50%。亜寒帯10%。
純生産量と分解期間からみた未分解有機物累積貯留量: 熱帯8ton(0.3年分)。温帯15ton(1年分)。亜寒帯100ton(9年分)。
貯留量から取り崩される量: 熱帯8ton。温帯7.5ton。亜寒帯10ton。
純生産量と分解期間からみた未分解有機物累積貯留量: 熱帯8ton(0.3年分)。温帯15ton(1年分)。亜寒帯100ton(9年分)。
貯留量から取り崩される量: 熱帯8ton。温帯7.5ton。亜寒帯10ton。
10. 無機態窒素?(生きてさえいれば)
炭素循環農法の土の、硝酸態窒素濃度の実測値は 0.23mg NO3-N /100g (乾土)以下。これは慣行(施肥)栽培における無機態窒素適濃度の1/40〜1/180 の濃度です。真に肥沃な土(養分供給力が高い土)=生きた土には、無機態窒素は殆ど存在しません。そして、収穫物の硝酸イオン濃度は、施肥栽培(日本の野菜の硝酸塩含有量)に比較して、一桁〜三桁も低い実測値です。
施肥栽培における無機態N適濃度: 作物により、アンモニア態N + 硝酸態N で 10〜40mg/100g(乾土)程度が必要と言われる(東京都農試) 農作物施肥基準(栃木県)。
日本の野菜の硝酸塩含有量: 国立医薬品食品衛生研究所(食品添加物含有量データベース) 生鮮食品中の硝酸塩,亜硝酸塩含有量。
日本の野菜の硝酸塩含有量: 国立医薬品食品衛生研究所(食品添加物含有量データベース) 生鮮食品中の硝酸塩,亜硝酸塩含有量。
水(土、植物体)の浄化が完璧に行われている証拠です。淡水資源の枯渇が懸念されていますが、農地は人為的な食料化装置であると同時に、淡水浄化装置でもあるのです。土でも作物でも硝酸態窒素が殆ど無いのは原理的には同じで、養分として使い切っている(生かしている)からです。
高炭素資材といえども最終的には無機化も行われます。でも、直ちに作物や雑草、土壌微生物が使い切れば残りません。作物に吸い上げられた窒素も、細胞に取り込まれ使い切れば、硝酸態窒素として数値には現れません。
しかし、これ程までに無機態窒素量が少ないのは、土壌中では無機化以前に微生物により再利用されているからと思われます。また、植物の低分子有機物(アミノ酸など)の利用が思いの外、大きいとも考えられます。
無施肥圃場の全窒素は、作物の養分ではなく養分供給を担う労働力です。絶対に殺してはなりません。生きている窒素には餌を与え、生かし続けなければ作物の養分供給が絶たれてしまいます。
慣行栽培(畑地)の平均全窒素量は0.25%(250mg/100g)。作物の窒素利用率は全窒素の4〜16%で、これを無機態窒素適濃度としている。
無施肥の全窒素量(実践例)は半分以下の0.11%(110mg/100g)。無機態窒素は全窒素の0.2%、全窒素の99.8%は作物が直接使えない生きている窒素。
無施肥の全窒素量(実践例)は半分以下の0.11%(110mg/100g)。無機態窒素は全窒素の0.2%、全窒素の99.8%は作物が直接使えない生きている窒素。
窒素が多いほど土壌微生物群や植物内生菌(エンドファイト)の窒素固定能は低下します。平均的な施肥圃場では無機態窒素を差し引いても、無施肥の倍の有機態窒素があります。しかし、大量の無機態窒素が、微生物による窒素固定能を著しく阻害し、ほぼ全量の有機態窒素を実質的な失業状態においているのです。そして、単に阻害するだけでなく、養分バランスを崩し病虫害、天災など一連の施肥障害を招きます。

土壌中に、作物にも微生物にも使われていない、遊離(無機態)窒素がなければ、養分バランスは崩れず、密植(写真:モドキの手抜き菜園 ^^; )ごときは、ストレスの内にも入りません。虫も菌もつかないのがその証拠(葉も対称に付いている)。密植のため葉は徒長気味ですが、適度な株間なら地面に張り付くように展開します。
すでに収穫適期、適度な株間の場合の倍の収量が見込めます。循環量は、見かけの窒素量(測定値)の40倍〜180倍で慣行並の収量になる計算ですから、アミノ酸なども含め更にその倍ほどあることになります。
作物は健康で活力があり、成長も早く、大きく育ち見かけも味も文句なし。貧弱なものは土の養分供給力に問題があるからで当然、味は落ちます。
無機態窒素が15mg/100g以上では、窒素量が増えるほどアンモニア態窒素の割合も増えると言われます。低C/N比、酸欠・腐敗が原因と考えられ、この測定例のようならアンモニア態窒素はほぼゼロ。考慮の必要なし。無機態窒素が無ければ、有機態窒素を殺して全窒素量を測定、というのは徒労。生きている窒素の循環量は、生き物(作物)にしてみなければ分かりません。
土壌中の全無機態N(硝酸態N + アンモニア態N): 無機態Nが15mg/100g(乾土)以下では、約90%が硝酸態N(全無機態N補正)。 土壌の無機態窒素濃度の簡易測定法(福岡農総試研報16 1997)。
施肥基準からすれば、0.23mg/100gの硝酸態窒素濃度で作物は育ってはいけない?ことになっています(笑)。しかし、事実は違います。施肥農法では、有機態窒素も無機態窒素も単なる物としか捉えていず、その生死を考えません。生かし方も知らず、殺すこと(無機化)しか考えていません。基礎となる「物の科学」が死物しか扱えないためでしょう。
無機態窒素量=死物(骸)量。生きていなければ、そこに有るだけの物で全てです。一定量がなければ不足することも、また事実。実際には微生物の全くいない土壌はなく、施肥農法で地力窒素と言われるものが大気中から捉えた窒素の、見かけ上の供給源です。施肥農法では虫(菌)だけではなく、この「生きている窒素」までも殺してから使おうとしています(乾土効果、土壌消毒などによる無機化)。殺し農法たる所以です。
全ての成分(養分)は、生きていることがより重要です。殺してしまってはただの「物」。余れば、作物中でも土壌中でも毒となり有害です。しかし、細胞や微生物などとして生きてさえいれば、たとえ大量にあって(いて)も害にならず、滞りなく物質循環が行われ、土壌中なら新たな養分の供給源ともなります。循環こそが供給力、永続性、そして「生」なのです。
11. 地力窒素?(減らしても減らしても・・・)
大量施肥による窒素のたれ流し(溶脱)の反省から、窒素を減らしてみても作物は育つ、更に減らしても、減らしても何故か育ってしまう(笑)しかも増収。ということに気付いたのが減肥栽培です。
何故か育ってしまう:
[水稲例] 堆厩肥施用量、化学肥料(N)需要量の減少(それぞれ60%、40%減)と、農薬出荷量の減少傾向(40%減)は一致する。ところが単位面積当たりの収穫量(玄米)は逆比例する形で増えている(約9%)。厳密には他の要因もあるため、これだけで相関を言えないが無施肥の実践例がそれを証明している。
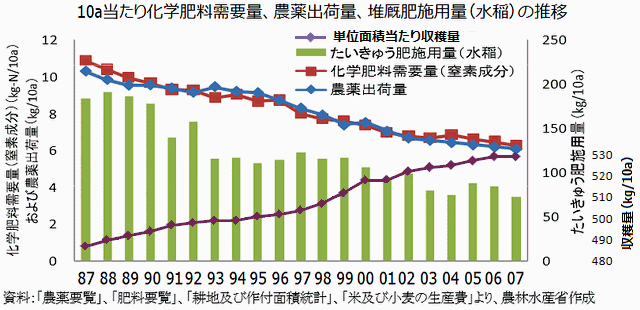
(単位面積当たり収穫量は農水省の資料に加筆)
[水稲例] 堆厩肥施用量、化学肥料(N)需要量の減少(それぞれ60%、40%減)と、農薬出荷量の減少傾向(40%減)は一致する。ところが単位面積当たりの収穫量(玄米)は逆比例する形で増えている(約9%)。厳密には他の要因もあるため、これだけで相関を言えないが無施肥の実践例がそれを証明している。
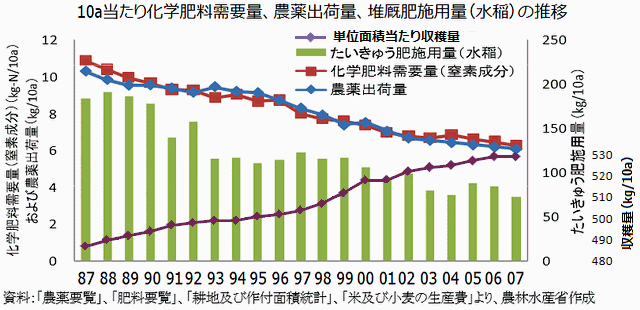
(単位面積当たり収穫量は農水省の資料に加筆)
減肥の結果が減農薬、増収なのです(でも不思議なことに腐植・施肥信仰の農学では「堆厩肥投入量を増やせ」と宣う)。これは、あくまでも無施肥への過渡期的な現象(栽培法)と捉えるべきものですが、このまま堆肥と化学肥料を減らして行けば転換手段としては取り組みやすく、多少時間がかかっても無理なくダイエットができるのが利点です。
施肥による窒素:
溶脱: 作物の施肥窒素利用率は平均で50%程度であるといわれている。控え目にみても、30〜40%が硝酸や亜硝酸の形で河川や湖沼、海に流入しアオコや赤潮の一因となっている。また、大気中にも亜酸化窒素ガス N2Oとして放出され、オゾン層の破壊、温暖化に関与していると言われている。
| 化学肥料 | 有機質肥料 | たい肥等 | 合計 | 全国合計 N千t | % | 全国作付面積 千ha | % | |
| 水稲 | 7.8 | 0.1 | 3.1 | 11.0 | 214.8 | 26.9 | 1953 | 52.7 |
| 畑作物 | 16.9 | 3.0 | 6.0 | 25.9 | 203.0 | 25.4 | 784 | 21.1 |
| 露地野菜 | 21.4 | 1.7 | 20.3 | 43.4 | 256.8 | 32.2 | 592 | 16.0 |
| 施設野菜 | 21.0 | 7.9 | 30.3 | 59.2 | 34.0 | 4.3 | 57 | 1.5 |
| 露地果樹 | 14.7 | 2.2 | 8.7 | 25.6 | 73.9 | 9.3 | 289 | 7.8 |
| 施設果樹 | 18.4 | 7.3 | 28.4 | 54.1 | 6.7 | 0.8 | 12 | 0.3 |
| 露地花き | 14.1 | 2.5 | 10.8 | 27.4 | 2.3 | 0.3 | 9 | 0.2 |
| 施設花き | 27.5 | 6.0 | 18.8 | 52.3 | 6.3 | 0.8 | 12 | 0.3 |
| 平均 | 21.5 | 総合計 797.8 | 100.0 | 3708 | 100.0 | |||
| 水稲以外 | 33.2 | 水稲以外 583.0 | 73.1 | 1755 | 47.3 |
減肥栽培では、地力窒素の発現を増やし施肥量を減らすと言います。減らしても育ちますから、確かに利用可能な窒素がどこからか発現しているわけです。しかし、減肥すれば、有機態、無機態窒素とも、無施肥の場合と同様に減ります。
ここで慌ててはいけません。土壌中の無機態(遊離)窒素は微生物や植物が使い切れなかった余分な窒素。過剰な有機態窒素はその予備軍。汚染源であり土壌環境悪化の元凶です。循環していない余剰分を減らすことが正常化なのです。高尿酸値や高血糖値、高コレステロール値を下げるのと同じです。
但し、単に下げれば良いというものではないのです。先ず、微生物に十分餌(炭素)を与え、遊離窒素の生物化=有機化(隔離)を行い使い切らせ、微生物の生息環境を整えながら、窒素固定(捕捉)能を活性化します。
同時にそれを妨げないよう減肥が必要です。つまり、減肥自体が減肥のための手段であり、更なる減肥を可能にします。最終的には、地力窒素だけで育つ無施肥栽培です。
要するに、カネ(可吸態や可吸化しやすい易分解性の窒素資材)を与えないことです。与えなければ失業状態の窒素(微生物)が働き、常時、安定的収入が得られます。安易に与えることが収入減(地力窒素の減少)につながり、更にカネをつぎ込むことになるのです。
| 無施肥 | 参考(畑地 標準的施肥/日本) | ||
| 全窒素 | 110mg/100g。 | 250mg/100g。 | |
| 無機態 (0.2%) | 施肥窒素 | ゼロ。 | 260〜590kg/ha(露地野菜434kg/ha)。 |
| 残存窒素 | 12kg/ha/耕土60cm(0.23mg NO3-N /100g以下)。 (無施肥では心土も使う) | 100〜600kg/ha/耕土25cm(5〜30mg NO3-N /100g)。 減肥:20〜100kg/ha。 | |
| 有機態 (99.8%) | 投入有機物 | 雑草、緑肥作物だけなら外部からの投入分ゼロ。 高炭素有機物(発酵処理)やキノコ廃菌床の使用(10t/ha)、15〜50kgN/ha(作物のN 吸収量の10%前後)。 | 70〜210kgN/ha(牛糞堆肥 10〜30t/ha)。 |
| 残存有機物(腐植) | 4%。 | 5.2%。 | |
| (土壌 C/N比) | 20 前後(温暖地の自然林野と同程度)。 | 12.1。 | |
| 地力窒素 | 固定窒素(非常在)。 (内生菌、根粒菌、藍藻など) | 作物のN 吸収量(300±150kg/ha)から投入、流入分を差し引いた量(作物や雑草の成長分として顕在化)。 (作物残滓や雑草、緑肥は貯留分として常在) | N 吸収量の 0〜50%。 (減肥:50〜90%)(水稲:50%前後) (但し施用有機物由来Nも含むため正味量は半分程度) |
| 流入 | 潅水および降下物 (紫外線、雷、車の排気ガス、工業煤煙などのNOx) | 地力の差により、保水力(固定大)や潅水量(流入小)が変わる。 全大気降下物/日本: 12kgT-N/ha/年 ・ 濃度 0.8mgT-N/l。 相当量が固定されると思われ、無施肥では無視できない。 | 溶脱量に加算される。 |
| 収支 溶脱 他 | N 収支 ±0 (滞りがない)。 ほぼゼロ。 生物による出入は大だが均衡。 | 施肥・固定・流入 390 - 吸収 300 = 入超(溶脱) 90kg/ha。 長期的にみれば平均施肥量の 30%弱が環境中に放出される。 生物による出入は小。 |
雑草や緑肥を栽培し、外部からの投入分ゼロで栽培を続けても、腐植量や全窒素量は、常にほぼ一定で殆ど変化しません。無施肥の場合作物が使う分の窒素は、土壌中に常在していないからです。
常在していなくても、土壌微生物や植物内生菌が大気中から常時固定しているため、その分は作物が使えます。この循環分だけが正味の地力窒素であり、土壌分析しても貯留分しか数値に現れません。
慣行農法では、「堆肥を施用し腐植を増やし、地力窒素の増強・無機化」などと言い、これを(これだけを?)地力窒素と思い違いをしているようです。
地力増強(土壌改良)のための投入資材や、その残存有機物から発現する分は、利益(地力窒素)を生み出すための投資分であり利益ではありません。地力窒素ではないのです。
見かけ上、投入分も固定分の一部(貯留分)と一緒に、有機物(微生物や雑草、作物残滓)の無機化という、かたちを通して発現して来るため、別々に測定することは不可能です。固定量から堆肥などの投資分を、差し引いて推定するしかありません。
堆肥を増やし窒素肥料(N総量)を30%(溶脱相当量)以上、減らしたからといって入超(溶脱)は解消しません。減肥により微生物の生息環境が良くなり、固定が増えるためです。70〜90%減らせば、ほぼなくなりますが、そこまでやるなら、いっそのこと無施肥にした方が賢明というものです(一般的堆肥C/N比20を40以上の超短期発酵資材に替えることが必須)。
12. 窒素固定?(窒素がほしければ炭素を)
豊かな自然を育む、大地の窒素の殆どは生物固定によるものです。作物の吸収量を満たすほどの固定が行われるかとの懸念は無用。窒素固定能を持つ細菌類(100属以上)は何処にでも、ごく普通に生息しています。| 共生的窒素固定菌 | 根粒菌(リゾビウム) ラン藻・放線菌(フランキア)などの一部 |
|
| 非共生的窒素固定菌 | 無機栄養微生物 | ラン藻・光合成細菌・硫酸還元菌・メタン菌などの一部 |
| 有機栄養微生物 | 好気性: アゾトバクターなど 嫌気性: クロストリジウムなど | |
知られている微生物は10%ほどと言われる、更に性質の分かっているのはその一部に過ぎない。研究が進めば、より多くの窒素固定菌が見つかると思われる。
生物が関与する窒素代謝(固定、硝化、脱窒)には細菌類だけでなく、菌類(カビ、菌根菌)など多くの微生物が関与している。
窒素固定には大量のエネルギー(炭素)を必要とし、宿主や環境中の有機物などの供給源を必要とする。
生物が関与する窒素代謝(固定、硝化、脱窒)には細菌類だけでなく、菌類(カビ、菌根菌)など多くの微生物が関与している。
窒素固定には大量のエネルギー(炭素)を必要とし、宿主や環境中の有機物などの供給源を必要とする。
よく知られている根粒菌以外に、痩せ地でも育つイネ科植物やサツマイモなどと共生する、植物体内共生細菌(エンドファイト)。単独で、あるいは共生生物の地衣類として、固定を行うラン藻(1000余種の約4%)など。固定量も根粒菌(植物のN吸収量の50%前後)に匹敵するものもあります。これらに働いてもらうのが自然農法です。
世界の窒素固定量は合計で 約3億t/年。農耕地における窒素循環の47%を工業的固定(化学肥料)に依存しています。工業的なアンモニア NH3固定技術の発明(ハーバー・ボッシュ 1917年)以前は、微生物固定による窒素だけで構成されていた人体構成窒素(核酸・アミノ酸・タンパク質など)もほぼ同率。半化学人間?(笑)。
工業的固定には、天然ガスを約 1600億m3/年を要し(天然ガス2,000m3/NH3 ton)、世界の天然ガス年間生産量の7.7%(総エネルギー消費量の約2%)に相当します。この分を生物的窒素固定に置き換えるには、平均で2倍にするだけで良いのです。土壌微生物による窒素固定量は炭素循環量にほぼ比例。炭素循環を効率化すれば容易に達成できます。
世界の窒素固定量(NH3換算)
生物的固定: 約1億8000万t/年 (60%)(農耕地 約9000万t/年)。
非生物的固定: 雷やオーロラ、燃焼(自動車、ボイラー)など 約4000万t/年 (13%)。
工業的固定(窒素肥料): 8162.5万t/年 2005 (27%)。
生物的固定: 約1億8000万t/年 (60%)(農耕地 約9000万t/年)。
非生物的固定: 雷やオーロラ、燃焼(自動車、ボイラー)など 約4000万t/年 (13%)。
工業的固定(窒素肥料): 8162.5万t/年 2005 (27%)。
しかし、生物は単独で生息することは殆どありません。窒素固定や代謝だけでも多くの種類の微生物が協働関係を保っています。特定の菌(根粒菌)を働かせようと考えてはいけません。
特に土壌微生物は何千という多様な種類が、お互いに依存、競争し、全体としては一つの共同体(複合微生物系)として、より高度な生命体を生かす方向に働いていています。個々の固定能は、それほど高くなくても、系として統合されれば、十分吸収量を賄える力を発揮します。
複合微生物系:微生物の働きを単独にではなく、微生物共同体(プロ集団)の協働と捉える。環境に応じた多様な系がある。過去存在しなかった人工化学物質でも分解できるようになるなどの未知の力も持つ。水処理、有害物質処理、水素生成など、目的に応じた最適な共同体の応用研究などが行われている。
作物の生育に必要な成分は多種です。より多くの微生物が同時に働き、適応範囲の広い微生物群=微生物叢(プロ集団の集まり)である必要があります。個々の微生物が必要とする養分は違いますが、微生物群を一つの生き物(複合体)としてみれば、餌はエネルギーに富む(高炭素)有機物だけで良いのです。
マメ科緑肥(根粒菌)は窒素固定に優れていても、微生物のエネルギー源である炭素固定力が低く、土壌環境を含めた微生物の総合的な力=地力を上げるのには不適です。しかもC/N比が低く腐敗しやすく、窒素固定がマイナスに作用します。
窒素がほしければ炭素を、炭素がほしければ窒素(肥効成分)を与えます。お奨めはしませんが、肥料に良く反応するエンバクやトウモロコシに、化学肥料や普通の堆肥(C/N比20前後)を与え炭素を大量に固定させて鋤込み、それを餌に窒素を固定させるという力技もあります。
極度の窒素欠乏(低バイオマス)の荒れ地などを短期間で肥沃化できます。これは例外的な肥料使用例で、施肥障害、硝酸汚染を避けるため必ず間接的、単発的に使います。作物の養分コントロールは、あくまでも微生物の仕事です。
農業関連の微生物の研究が盛んに行われています。ただ、微生物の実用性試験を参考にする際には注意が必要で、微生物に餌もやらず、生息環境も整えず効果云々、生産性比較。また同様な、自然農法の可能性(無施肥、無防除)の試験や、その生産物の質、環境負荷などに対する試験(分析、比較)は無意味です。
逆に十分な餌を与えれば、微生物を使わなくても良い結果が出ます。それを特定の微生物や複合微生物製剤の効果との喧伝も要注意です。
慣行農法と自然農法の、表面上の違いは無施肥・無施水・無防除ですが、本質的な違いは死人(菌、物)を働かせないことです。微生物がまともに生きられないような条件下での試験では参考にならないのです。
でも一応、真面目な研究なだけに、その結果を消費者や農業者、農学生が鵜呑みし、一般で信じられているという笑えない事実があります。無施肥で育つ仕組み(生きている系としての微生物の働き)を理解していないためです。微生物さえ使えば奇跡が起き、自然農法なら魔術が使える。わけではありません(笑)。
13. 気温上昇期の土壌硬化?(表裏の逆転)
転換期の土壌では春先に、細菌類の活動が活発化すると一過性の土壌硬化現象が現れることがあります。土が凍結してしまう寒冷地、過乾燥地などの微生物全般が冬期活動できない地域や、逆に通年活動可能な高温地域では、あまり見られない現象です。中緯度地方の冬期は、細菌類(バクテリア)の活動は抑えられ、低温に強い菌類(キノコ菌など)だけが働く状態となり、菌類優勢(発酵)状態ですから冬野菜は比較的よくできます(味も良い)。難分解性有機物の分解は進み、団粒化成分でもある分解生成物が菌類に消費されず蓄積されるところに問題があります。
難分解性の炭素資材も、菌類の分解作用で易分解性へと変わると共にC/N比も下がり、浄化不十分(無機態窒素の残存)と相まって、細菌類の活動条件に不足するのは温度だけとなります。
そこへ春先の気温上昇、適度な降雨があると、爆発的に細菌類が増え発酵・分解型から一転、腐敗・分解型へと場の転換が起きます。ここでEM菌などの微生物資材を使うと、腐敗生成物だけでなく僅かに残った団粒化成分までも食い尽くし、更に土を固め通気性を悪化させます。団粒化どころか腐敗要因の増強です。
この際、C/N比を上げようと、難分解性の高炭素資材を併用しても、資材全体が同時に分解せず菌類の分解生成物や、易分解性有機物(若い雑草・緑肥作物、残滓)だけが急速に、腐敗・分解され土壌が硬化します。パーフェクトなキノコ廃菌床でも同じことです。
それぞれの炭素資材の分解が一定の流れとならずバラバラに行われ、各資材の持つ特性が互いにマイナスに作用してしまうのです。腐敗分解では無機化し肥効を発現、施肥害がでます。
これは地温変動が激しい表層部で起きます。対処法はマルチなどで雨を防ぎ土を濡らさない。表層を軽く起こし空気を入れる。などです。
同時期に更に、まとまった降雨があると土壌深層部でも似たような現象(一時的な水質悪化)に伴う腐敗が起きます。土壌深部は冬期(乾期)でも地温変動は僅かで問題にはなりません。しかし、乾燥のため酸素量が増え菌類が活性化、分解成分が蓄積されます。
そこへ降雨により過去に蓄積された、硝酸や腐敗成分が溶け出すと同時に、表層が水で蓋をされ深部は酸欠状態になり腐敗状態に陥ります。こちらは一連の基本的な技術で深部の酸素量の変化を減らし、時間をかけて浄化するしかありません。
微視的に見れば、先ず(表で)好気性菌(主役)が働き、酸欠状態になった所(裏)で嫌気性菌(裏方)が活躍するのが無駄、無理のない流れです。微生物はそれぞれ働く「場」が違い、本来の場で働かないと結果はマイナスになります。硬化現象はこのような一時的、変則的な分解作用による場の転換。表裏の逆転現象と考えられます。
14. 砂漠化?
陸地で砂漠化しないのは完全な砂漠だけ、太陽系規模での気候変動による砂漠化を別にすれば、半砂漠や砂漠化しやすい地域での人の活動が原因。その原因は、過放牧(34.5%) + 過伐採(29.5%) + 過耕作(28.1%) = 合計(92.1%)と言われています。しかし、これは結果です。そこに至る、根本的な原因を見極めなければなりません。現在、世界経済のグローバル化で、異常な物質(食糧)循環が起きています。自由貿易は食糧を食糧以外の「世界経済支配の戦略物質」に変えてしまいます。そしてこれが急速な砂漠化の真の原因と言われています。
これは社会構造の問題であり、自然農法と全く同じ「視点の転換」が起きない限り、真の解決は望めません。実際の食糧生産を通し「土と意識」の両面の転換を図りながら、砂漠化阻止・復元を同時進行で行わなければなりません。
自由貿易は食糧を: 現代砂漠化の原因は自由貿易 http://env01.cool.ne.jp/ss04/ss043/ss0431.htm(環境経済・政策学会 投稿論文 2002年5月)槌田敦(名城大学経済学部)
社会の発展 → 人口増加 → 森林伐採(耕地化・薪炭材採取) → 過耕作(潅漑 → 塩類蓄積) → 植生の退化(草地化) → 過放牧 → 被覆植物消滅 → 気候変動・浸食・干ばつ → 砂漠。人口増は社会問題。森林伐採・耕地化はある程度やむを得ません。途上国での過伐採の主因は調理用(全消費量の90%)の薪採取。これは太陽熱調理でほぼ解決できます。先進国の援助があれば太陽光発電、風力なども使えます。
問題は次の過耕作です。典型的なパターンは炭素の無駄遣い(焼く、可食部以外の持ち出し、放置)や補給を怠った不適切な耕作の結果、土壌微生物相の弱体化・土壌物理性の悪化。窒素の固定・保持量減少、植生の退化・単純化(草地化)。そして、貧弱な植生でも飼育可能な羊や山羊などの過放牧。習性上、草を根こそぎ食べてしまい緑が消えます。
被覆植物が消えた大地は、保水・保温力を失い大気への水蒸気の供給も減り小雨化。地表面は昼夜、年間の寒暖差が激しく、穏やかな気候から降れば豪雨、照れば干ばつと砂漠型の気候へと進みます。
砂漠化の定義(UNCCD 1994年 砂漠化対処条約):
乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域における様々な要素(気候変動および人間の活動を含む)に起因する土地荒廃。
土地荒廃の定義:
乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域において、土地の利用又は単一の若しくは複合的な作用(人間活動及び居住形態に起因するものを含む。)によって天水農地、潅漑された農地、放牧地、牧草地及び森林の生物学的又は経済的な生産性及び複雑性が減少し又は喪失することで次のようなものをいう。
(1)風又は水による土壌の侵食。
(2)土壌の物理的、化学的及び生物学的特質又は経済的特質の悪化。
(3)長期的な自然の植生の喪失。
砂漠化・土地荒廃問題に関するページ 世界砂漠化・干ばつ記念セミナー記録(砂漠化と土地荒廃の概念)より抜粋
乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域における様々な要素(気候変動および人間の活動を含む)に起因する土地荒廃。
土地荒廃の定義:
乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域において、土地の利用又は単一の若しくは複合的な作用(人間活動及び居住形態に起因するものを含む。)によって天水農地、潅漑された農地、放牧地、牧草地及び森林の生物学的又は経済的な生産性及び複雑性が減少し又は喪失することで次のようなものをいう。
(1)風又は水による土壌の侵食。
(2)土壌の物理的、化学的及び生物学的特質又は経済的特質の悪化。
(3)長期的な自然の植生の喪失。
砂漠化・土地荒廃問題に関するページ 世界砂漠化・干ばつ記念セミナー記録(砂漠化と土地荒廃の概念)より抜粋
土地荒廃の定義に示されている三つの項目は「炭素循環の極度な低下」により派生する現象です。過耕作は炭素の相対的過剰消費。一連の砂漠化現象の真の直接原因は炭素不足。炭素循環農法(耕作=炭素固定)=焼かない焼き畑農法の出番です。
砂漠化の危機に直面しているのは、主に降雨が一時期に偏ったり、降雨量が少ない地域。雨水の浸透性、保水性を高め逃さないよう、炭素循環を十分行うことが重要になります。焼き畑が可能な地域なら潅漑の必要はありません。以前が森林や草地だったのであれば、それを維持するだけの最低限の条件(降雨量など)は揃っているからです。
潅漑が不可欠な乾燥、半乾燥地域での塩類蓄積は、肥料抜きの点滴潅漑や保水性資材の埋設などの技術が応用可能。潅漑農業の多くは多少なりとも、近代農業の技術を取り入れていると思われます。十分な炭素循環により節水。また、アルカリ土壌を中和しpHも下がります。真の自然農法は「自在」技術を選びません。
砂漠化の人的要因は「貧困・餓え」。保全と同時に食糧増産ができなければ意味をなしません。また、カネ・技術なしで過耕作を回避し、鍬一本で増産できる農法が求められます。ちなみに、砂漠の緑化は砂漠化した土地に対してのもの、元からの砂漠では炭素循環に必要な条件が揃わず、経済性を無視しない限り緑化は無理です。
技術的には、さほど困難ではありません。難しいのは技術を活かせる場の整備、意識の地動説転換。これが前提条件です。これがない限り戦争同様、餓えも砂漠化も解決しません。
現状のままでは、カネがカネを吸い寄せ経済大国、巨大資本が緑を食い尽くします。内戦が経済を疲弊させ、軍事費が国家を押しつぶします。正義(自己中心)を振りかざし、悪を排除(対症療法)の天動説では、何時まで経っても真の解決はあり得ません。
カネがカネを:
「物」は濃(高)い方から薄(低)い方へ。物ではない「“もの”」や、それが作用する時は、逆に薄い方から濃い方へ流れる。カネは物ではない(相対的価値を表す情報)それ故、ない方からある方へ流れる。これは善悪の問題ではなく、非物質世界の法則。
「物」は濃(高)い方から薄(低)い方へ。物ではない「“もの”」や、それが作用する時は、逆に薄い方から濃い方へ流れる。カネは物ではない(相対的価値を表す情報)それ故、ない方からある方へ流れる。これは善悪の問題ではなく、非物質世界の法則。
15. 地味?(どうせ作るなら・・・)
栽培作物(特に永年作物)を選ぶ際に無視しできないことがあります。同じ作物を同地域で、同じ者が作っても(同技術)、同じように美味しい物ができるとは限りません。「地味」の違いなどと言われ、昔から良く知られていている現象です。これは、単に土質の違いだけではなく、他にも多くの要素が関係しています。地味に合わせて栽培作物を選んでも別段、手間暇、カネがかかるわけではありません。どうせ、作る(食べる)なら、無駄な努力(自然に逆らうための労力)をすることなく、高品質で美味しい物を「楽して」作る(選ぶ)。これも自然の摂理(命を生かす仕組み)に従うということです。
地味:
母岩(火成岩、火山灰、水成岩など)や生成過程(風化、溶脱・集積、堆積など)。緯度・標高や地勢(地形・向きなど)からの気象(降水量・季節変化、日照量・強度・時間帯、気温・地温・日内変化、風向・風力、潮風など)。更に土壌の状態を表す、土の三相=液相・気相・固相、及びその性状(粘土、砂、礫、腐植など)。そして第四の相(生物相=バイオマスとその主要種)。肥効成分・拮抗成分(N・P2O5・K2O、ミネラルなど)やペーハー(pH)。相似象学的にみた土地の優劣(大気・大地の電位傾斜、いやしろ地・けがれ地など)。これらの多くの要素が複雑に絡み合い成り立っている。
母岩(火成岩、火山灰、水成岩など)や生成過程(風化、溶脱・集積、堆積など)。緯度・標高や地勢(地形・向きなど)からの気象(降水量・季節変化、日照量・強度・時間帯、気温・地温・日内変化、風向・風力、潮風など)。更に土壌の状態を表す、土の三相=液相・気相・固相、及びその性状(粘土、砂、礫、腐植など)。そして第四の相(生物相=バイオマスとその主要種)。肥効成分・拮抗成分(N・P2O5・K2O、ミネラルなど)やペーハー(pH)。相似象学的にみた土地の優劣(大気・大地の電位傾斜、いやしろ地・けがれ地など)。これらの多くの要素が複雑に絡み合い成り立っている。
適地適作(気候・土壌・経済圏)と言いますが日本のように、土壌の生成過程が複雑に入り組み、変化に富んだ地勢では、画一的にその条件を判断できません。もちろん、全ての生き物を生(活)かせば多少、条件(地味)が悪くても、その条件の範囲内で最良の作物ができ、それなりに美味しい物ができます。しかし、より良質で美味しい物を作ろうと思えば、微妙な地味の違いを無視できません。
土は土壌改良などで人為的にある程度変えられます。電位傾斜や微気象も、多少はコントロールできます。簡単に変えられないのが緯度・標高や地勢から来る日照変動。昼夜・季節の温度変化など、全般的な気象です。
多くの作物が、昼夜の寒暖差が大きいほど美味しくなるということはよく知られています。更に日照強度(緯度や南北面の違い)や日照時間帯の差(東西面の違い)の影響も大きく、その対応関係は、収穫物の「色」で判断すれば良いと言われています。
色:
細胞の培養において照明の色の違いによって増殖スピードに差があることが知られている(青系より赤・オレンジ系の方が良い)。これは、生物が感覚以前のレベルで色温度K(ケルビン)を含めた「色」に感応しているためと思われる。
緑色の葉野菜は日照が強すぎると風味を損なう(特に低緯度地方)。果菜類や果実など、緑色の物(キュウリなど)は主に朝日を受けるのが良い。黄色の物(柑橘類など)は日中の強い光が必要。赤色の物(トマト、イチゴ、リンゴなど)は夕日がしっかり当たること。白(青)や黒い物(根菜類や種=穀類など)は、これらの集大成であり文字通り「結・果」。全体の日照の影響が大。
細胞の培養において照明の色の違いによって増殖スピードに差があることが知られている(青系より赤・オレンジ系の方が良い)。これは、生物が感覚以前のレベルで色温度K(ケルビン)を含めた「色」に感応しているためと思われる。
緑色の葉野菜は日照が強すぎると風味を損なう(特に低緯度地方)。果菜類や果実など、緑色の物(キュウリなど)は主に朝日を受けるのが良い。黄色の物(柑橘類など)は日中の強い光が必要。赤色の物(トマト、イチゴ、リンゴなど)は夕日がしっかり当たること。白(青)や黒い物(根菜類や種=穀類など)は、これらの集大成であり文字通り「結・果」。全体の日照の影響が大。
この色との関係は、適地適作の基準の一つでもあり、消費者にとっては、より美味しい作物が採れる産地を知る基準になります。またこれは、最適な収穫の時間帯や、食べる時間帯とも関係(一致)しています。生産者(作物を選ぶ)、消費者(産地を選ぶ)共に、自然の精妙さを知り、それを活用したいものです。
16. 単一作物栽培?(潜在力さえあれば・・・)
大面積の単一作物栽培(モノカルチャー)は「緑の革命」でも明らかなように、種々の弊害から初期の目的を達成していません。一般には多様性を無視した、単一作物栽培が問題なのだと思われています。しかし、それ自体が問題なのではありません。問題は「施肥・施水・防除=殺し農法」の技術によっているからなのです。施肥により土壌微生物の多様性が失われた結果です。
モノカルチャー(mono culture):
植民地時代、サトウキビ、コーヒー、天然ゴム、穀類などの商品化に向く作物を集中的に大規模生産させた強制栽培制度があげられる。アメリカの食糧による世界制覇の一環として、ノーマン・ボーログ博士(1970年緑の革命でノーベル平和賞受賞)を中心に、1940年代にメキシコで始めた「緑の革命」もモノカルチャーの代表的なものである。
緑の革命(Green Revolution):
メキシコ後も発展途上国の穀類など増産のため、アメリカの財団と国際開発局、世界銀行などが集結した農業改革が、1980年代後半から発展途上国でも広く行われた。化学肥料と殺虫剤の大量投入、潅漑施設や大型農業機械、F1種導入などにより増収を目指したが失敗。持続不可能で永続性のない農業技術として多くの批判がある。現在も遺伝子組み換え品種導入などによる、第二の緑の革命が画策されているが多方面から疑問視されている。
初期の目的:
効率的な食糧増産・飢餓撲滅。市場開放・食糧による経済的支配。皮肉なことに「緑の革命」による飢餓撲滅の失敗が、もう一方の目的である大国、巨大資本による経済的な支配をより強固なものにした。
種々の弊害:
水の大量消費と汚染、塩害。土壌の疲弊・農耕地の放棄、砂漠化。新たな森林伐採、環境破壊。商品価値のある特定作物に偏り在来栽培種の多様性喪失。従来の自給自足型農業とそれに伴う文化の崩壊。大量生産から受給のアンバランス、市場価格暴落。高コストの近代農業は経済格差を拡大し大多数の農民は貧困化。資材購入のため農地を担保に借金・返済不能・農地の放棄・離農。増産は一時的、その後は導入以前より生産性が落ちる。たとえ増産できても、グローバル化した市場経済下で大資本の支配下に組み入れられ、大量生産された農産物は輸出。貧しい自国民には買えず、飢餓はむしろ拡大したと言われている。
植民地時代、サトウキビ、コーヒー、天然ゴム、穀類などの商品化に向く作物を集中的に大規模生産させた強制栽培制度があげられる。アメリカの食糧による世界制覇の一環として、ノーマン・ボーログ博士(1970年緑の革命でノーベル平和賞受賞)を中心に、1940年代にメキシコで始めた「緑の革命」もモノカルチャーの代表的なものである。
緑の革命(Green Revolution):
メキシコ後も発展途上国の穀類など増産のため、アメリカの財団と国際開発局、世界銀行などが集結した農業改革が、1980年代後半から発展途上国でも広く行われた。化学肥料と殺虫剤の大量投入、潅漑施設や大型農業機械、F1種導入などにより増収を目指したが失敗。持続不可能で永続性のない農業技術として多くの批判がある。現在も遺伝子組み換え品種導入などによる、第二の緑の革命が画策されているが多方面から疑問視されている。
初期の目的:
効率的な食糧増産・飢餓撲滅。市場開放・食糧による経済的支配。皮肉なことに「緑の革命」による飢餓撲滅の失敗が、もう一方の目的である大国、巨大資本による経済的な支配をより強固なものにした。
種々の弊害:
水の大量消費と汚染、塩害。土壌の疲弊・農耕地の放棄、砂漠化。新たな森林伐採、環境破壊。商品価値のある特定作物に偏り在来栽培種の多様性喪失。従来の自給自足型農業とそれに伴う文化の崩壊。大量生産から受給のアンバランス、市場価格暴落。高コストの近代農業は経済格差を拡大し大多数の農民は貧困化。資材購入のため農地を担保に借金・返済不能・農地の放棄・離農。増産は一時的、その後は導入以前より生産性が落ちる。たとえ増産できても、グローバル化した市場経済下で大資本の支配下に組み入れられ、大量生産された農産物は輸出。貧しい自国民には買えず、飢餓はむしろ拡大したと言われている。
多様性は「生」その喪失は「死」の方向を指します。嘗てない急速な種の絶滅が進行している現在、多様性の保全は急務です。保全の重要性が叫ばれ、条約もできています。しかし、単に表面上の多様性だけを保とうとするのは徒労。生物の生存を可能にしているのは、それを支える「場=環境」があるからで、その場の保全と直接眼に見えない「潜在力=生物界の底辺(微生物の多様性と量)」を高める以外に真の保全策はありません。眼に見える部分は結果であり、原因ではないからです。
種の絶滅:[野生生物種の絶滅より抜粋要約]
恐竜時代以降、1年間に絶滅した種の数は、恐竜時代は1年間に0.001種、1万年前には0.01 種、1000年前には0.1種、100年前からは1年間に1種の割合で生物が絶滅している。現在では1日に約 100種(1年間に約4万種)。たった100年で約4万倍以上のスピードになり現在も、なおそのスピードは加速を続けている。このままでは25〜30年後には地球上の全生物の1/4が失われてしまう計算になる。
条約:
生物の多様性に関する国際条例条約(略称:生物多様性条約 CBD=Convention on Biological Diversity)。バイオ企業などによる途上国の遺伝資源の独占防止、バイオテクノロジーによる種の多様性駆逐などの監視するため、生物の多様性を「生態系、種、遺伝子」のレベルでとらえ、「生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝子資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」を目的とする。
恐竜時代以降、1年間に絶滅した種の数は、恐竜時代は1年間に0.001種、1万年前には0.01 種、1000年前には0.1種、100年前からは1年間に1種の割合で生物が絶滅している。現在では1日に約 100種(1年間に約4万種)。たった100年で約4万倍以上のスピードになり現在も、なおそのスピードは加速を続けている。このままでは25〜30年後には地球上の全生物の1/4が失われてしまう計算になる。
条約:
生物の多様性に関する国際条例条約(略称:生物多様性条約 CBD=Convention on Biological Diversity)。バイオ企業などによる途上国の遺伝資源の独占防止、バイオテクノロジーによる種の多様性駆逐などの監視するため、生物の多様性を「生態系、種、遺伝子」のレベルでとらえ、「生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝子資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」を目的とする。
炭素を十分循環させれば、土壌微生物相は多様化しバイオマスは増大、地上からは虫(菌)や鳥獣なども消え、作物だけになり栽培種の制約も殆どなくなります。このような何でも育てられる土であれば、何がどのように植えられていても構いません。農耕地という制約の範囲内で地下生物群として、生物多様性は保たれるのです。
潜在力さえあれば見かけなど、どうでも良いのです。他種類混作でも、単一作であっても、栽培作物の種類の多寡による差は見られません。もちろん、大面積・単一作物の連作であっても環境破壊は起きません。サトウキビでは既にそれが証明されています。
サトウキビでは:
一般的に行われてきた火入れ収穫(収穫前に葉を燃やし除去)を止め、火入れせずそのまま収穫するグリーンケーン収穫(梢頭部や葉をそのまま畑に残す)により肥沃化し、無施肥・無施水・無防除を可能にした。土壌物理性も改善されて雨水が全てその場に浸透するため等高線栽培も不要。
一般的に行われてきた火入れ収穫(収穫前に葉を燃やし除去)を止め、火入れせずそのまま収穫するグリーンケーン収穫(梢頭部や葉をそのまま畑に残す)により肥沃化し、無施肥・無施水・無防除を可能にした。土壌物理性も改善されて雨水が全てその場に浸透するため等高線栽培も不要。
在来の栽培種の多様性(遺伝子)喪失の問題もありますが、それは栽培や技術面の問題ではなく、文化や経済の問題です。もちろんこれも、それを維持しする「場」が崩壊しているからに他なりません。その原因の一つに、単一作物栽培があるのは確かです。でも「衣食足りて礼節を知る」。先ず肥料、農薬、農業資材の支配からの脱却。そして十分な食糧を確保し飢餓を無くし、経済的な自立を果たさない限り、伝統的な農業やその文化、種の保存など覚束ないでしょう。
もっとも衣食足りた結果、礼節はどこかに消えてしまったのが先進国の現状ですが・・・。これは「物」しか見ない「意識の天動説」の典型例とも言うべき、市場原理主義・経済至上主義ゆえのこと。あらゆる面で世界規模の画一化(モノカルチャー化)が進み、憂慮すべき状態ですが、ここでは割愛。
17. 種苗の肥毒?(過剰栄養障害)
土の肥毒と言われているものは施肥・腐敗に伴う過剰栄養や腐敗毒成分、土壌微生物相の単純化・弱体化、有害センチュウなどの増加、土壌バイオマスの減少、土壌物理性の劣悪化などによる一連の施肥障害。作物や種苗の肥毒も、もちろん施肥障害です。しかし、物理的な“もの”によるのではなく、過剰栄養状態の継続による細胞レベルでの形質的変化・異常。過剰栄養障害と考えられます。要するにメタボリックシンドロームです。
幼少時から常に、ファーストフードなどのジャンクフード(ガラクタ食品)の類を食べていた女性が妊娠を機に、胎児に悪いだろうと自然食に替えました。そして無事出産、その後も自然食を続け母乳で育てました。
しかし生まれた子供は出生後、直ぐにアトピー性皮膚炎を発症。母親が少しでも肉・卵・乳製品などを摂ろうものなら、子供のアトピーはたちまち悪化。もちろん人工乳も試してみましたがダメ。悩み苦しみ悪戦苦闘、やがて離乳の時がきました。
ところが、あら不思議。母乳を止め離乳食にした途端、たちどころにアトピーが治ってしまったのです。何のことはない原因は良かれと思い与え続けたメタボ母乳?。つまり母乳の肥毒。これも過剰栄養障害の一つ。母親にはアトピーもメタボの兆候も全くみられませんが、正常な母乳が作れない体(メタボ腸?)になっていたと考えられます。
妊娠以前のジャンクフード(高脂質、高糖分、高カロリー、高塩分、高い加工度)による情報汚染=環境適応?のため、どんなに良いもの(自然食)を食べても、母体での処理が不十分で、アレルゲンが母乳に移行してしまったようです。子供の皮膚炎の侵出液は母親が食べたものの臭いがします。
胎児に悪いだろうと:
現代人の多くは、既に農薬や腐敗産物、食品外の添加物などの毒に対する耐性を持っている。
母乳に移行:
薬毒物や老廃物は主に糞や尿あるいは胆汁(糞)に排泄されるが母乳、腸液、唾液、胃液、汗、 呼気なども排泄経路である。特に、生体濃縮が起きる有害な脂溶性成分(人工的な化学物質、ダイオキシン類などの難分解性有機化合物や重金属、放射性物質)が母乳の脂質に溶けて排出され問題となる。
現代人の多くは、既に農薬や腐敗産物、食品外の添加物などの毒に対する耐性を持っている。
「妊娠後期と授乳期に揚げ物やスナック菓子、ファーストフードを多く摂取した母親から生まれた子供は、摂取しなかった母親から生まれた子供に比べアトピー性皮膚炎になる頻度が低い可能性が明らかとなった。」「授乳中の母親が卵や牛乳を摂取した方が、子どもが卵や牛乳に対するアレルギーになりにくい可能性が示された。」ソバなど他の食品アレルギーとの関連性はない。脂質の摂取と子供の皮膚の質との間の相関や、母体を通しての経口免疫寛容(徐々に摂取することでアレルギーが起こらなくなる)が示唆される。(国立成育医療センター研究所 松本らグループ)これは要するに、ジャンクフード耐性?。また、胎児、乳幼児時代の過剰栄養摂取が成人になってからのメタボと相関があると言われている。何を食べても平気(一時的)になればよいというものではない。ツケを後から、まとめて生活習慣病、自己免疫疾患、うつ病、死などとして払うことになる。
母乳に移行:
薬毒物や老廃物は主に糞や尿あるいは胆汁(糞)に排泄されるが母乳、腸液、唾液、胃液、汗、 呼気なども排泄経路である。特に、生体濃縮が起きる有害な脂溶性成分(人工的な化学物質、ダイオキシン類などの難分解性有機化合物や重金属、放射性物質)が母乳の脂質に溶けて排出され問題となる。
原始的な生物であるキノコ菌(菌類の一種)でも、過剰栄養による障害がみられます。高養分下で何代も菌糸の拡大培養をすると弱ってしまい、容易にバクテリアに冒されたり、キノコが十分成長せず早期に胞子を放出して、子孫を残そうとします(野菜の早期トウ立ちと同現象)。
キノコ菌(糸状菌)は、その名の通り同じ細胞が糸状に連なって一つの個体を形成。外観が違う子実体(キノコ)=胞子製造・放出器官でも細胞は同じです。一旦弱った菌体の何処から断片を採取して、組織培養を繰り返しても形質は変わらず、個体の全細胞が異常なのです。
これの回避法は、種菌の維持には低養分で培養し、実際にキノコを発生させる栽培時には、逆に高養分環境や使う資材(オガコの樹種、栄養剤など)に慣らしてから使います。
それでも弱ってしまった場合は、低温下(5゜C)に長期間(1〜数年)放置します。すると面白いことに、元の性質を取り戻すことがあります。低温(冬)=代謝抑制と低養分(飢餓)刺激が、無施肥と同様な効果を誘発。これは原理的には断食、細胞レベルでのメタボ癖?の治療法です。
最新の研究成果として、環境に対する適応力のような後天的な獲得形質がDNAに記録されることが分かっています。ということは全ての生物が持つ特性。メタボも生物進化の一要因。千、万年後にはメタボでなければ不健康なんてことに?(笑)・・・。
18. 種子の選択?
市販の種子は何でも使えるとは言っても、もちろん怠け癖?が付いてしまい、プロの場合は使えないものもあります。鍛え直す(自家採取)には、時間がかかり少々面倒です。できるだけ早く知る方法が必要です。超低養分で苗を育てると何となく様子がおかしい、成育むらがある、枯れてしまう。という場合があります。正常な種子なら、葉が小さくても均一にムラなく育ち、簡単に枯れたりはしません。この場合は、種子に肥毒があると考えてよいでしょう。
これは、極限状態でなければ現れない現象です。従来の養分たっぷりの育苗法では、育苗段階で種子の良し悪し(向き不向き)を知ることは困難です。
育苗段階で僅かでも様子がおかしい場合は、定植後も正常に育たないと考え、早めに廃棄して次の対策を講じた方が経済的損失が少なくて済みます。
播種後、一旦枯れても新葉が出るようなら、それなりに育ちますが問題のある苗は使わない方が無難。やむを得ない場合は枯れるものは、できるだけ枯らし残ったものだけ植えるようにします。つまり、自然に聞く(任せる)わけです。
面白いことに、慣行施肥栽培で評判が良いものが以外とダメで、ダメと言われるものが良いことがあります。過剰栄養に適応し、直接使える肥料が十分無ければ育ち難いものと、適応できず過剰栄養に弱いものがあるということです。これも種子選びのポイントの一つです。
種子の異常を云々するには、先ず圃場全体が均一に、完全に浄化されていなければなりません。作物の様子が、おかしくても何が原因か特定できないような状態では話になりません。
はっきり分かるようになるのは、収量が慣行農法を超えて、季節による味の変化も完全になくなり、早くても転換後、2年目の後半あたりからです。
| 4 | − | 9 | 2 | |
| | | | | |||
| 3 | − | 5 | − | 7 |
| | | | | |||
| 8 | 1 | − | 6 |

