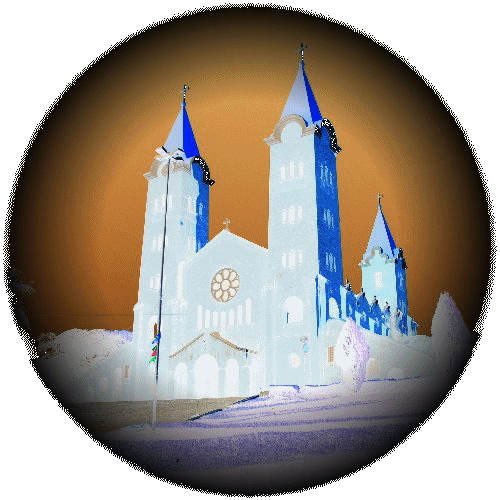実践3(2009日本 春)
餌が足りない
|
飢餓状態(完全浄化に至らない)
 写真(右)は傾斜地の畑でよく見られる現象です。この例は、60数年前に切り土・盛り土して造成した畑。餌不足のため圃場全面の養分濃度が低く、切り土し根圏が浅い所では、極度な養分不足。盛り土部分で根圏が深いところでも、まだゝ不足。
写真(右)は傾斜地の畑でよく見られる現象です。この例は、60数年前に切り土・盛り土して造成した畑。餌不足のため圃場全面の養分濃度が低く、切り土し根圏が浅い所では、極度な養分不足。盛り土部分で根圏が深いところでも、まだゝ不足。葉色の濃淡や成育の良否は、柔らかい土の層の深さ=作物が使える土の量=根域容積の反映。無施肥での成育程度は、養分濃度と根圏容積の積に比例します。
また、少し虫にも食われています。これは、自然猿真似農法で無防除を困難にしている典型的な飢餓現象。微生物の餌不足=養分不足=栄養失調のため、作物の活力が落ち、更に土壌中では、軽い腐敗と浄化が繰り返されているためと考えられます。
餌(作物残滓など)で微生物が増える → 腐敗成分の生物化=浄化 → 微生物が増えたため餌不足 → 微生物の餓死 → 腐敗。この繰り返し。飢餓状態では、何時まで経っても完全浄化に至りません。
生きている土は大食漢(痩せ地ではハーブ化)
 写真(左)スギナ(原始的な植物)の繁茂、小さく黄色い葉、早期の薹立ち(とうだち)、ネギ科の葉先端の枯死。これほど痩せるまで「辛抱」できたのは、自然農法(猿真似)などの知識や経験の賜・・・?。と感心するほど。
写真(左)スギナ(原始的な植物)の繁茂、小さく黄色い葉、早期の薹立ち(とうだち)、ネギ科の葉先端の枯死。これほど痩せるまで「辛抱」できたのは、自然農法(猿真似)などの知識や経験の賜・・・?。と感心するほど。それなりに、土はきれい。しかし、これではハーブ?。野菜もハーブも、腐敗のないきれいな土であることが重要ですが、要求される肥沃度は違います。
これではハーブ?:
野菜は肥沃な土、ハーブは痩せ地で育てる。痩せ地の野菜は硬くてクセが強く、ハーブ化(野生化)。逆に、ハーブを肥沃地で育てると独特の風味が薄らぎ野菜化、ハーブとしての特徴が失われてしまう。ハーブは圃場を別にするか、圃場の周辺部(土手)などを使う。
野菜は肥沃な土、ハーブは痩せ地で育てる。痩せ地の野菜は硬くてクセが強く、ハーブ化(野生化)。逆に、ハーブを肥沃地で育てると独特の風味が薄らぎ野菜化、ハーブとしての特徴が失われてしまう。ハーブは圃場を別にするか、圃場の周辺部(土手)などを使う。
殆どの実践者の圃場が極度の低養分状態。予想はしていたものの実際は惨憺たる状態。写真(上)のように物理的な「土の中の状態」が成育むらとして、はっきり作物に反映されるほど痩せています。
なぜ、このような状態に・・・?。早い話が、ここに書いてある通りにやっていない!。土壌中の生きものに餌を十分与え飼育するという感覚が欠如している証拠。生きている土は大食漢。餓死させてはなりません。
餌を与えれば、微生物が食べて頭?(口?)数が増る → 増えた分だけ餌の必要量も増える → 更に数が増る → 餌が・・・。という増殖サイクルに合わせ、必要最低限の量に達するまで、餌を増やし続けなければなりません。
但し、土壌微生物と植物の食物連鎖が構築され、物質循環が円滑化すれば有機資材の外部からの持ち込み投入量は減らせます(緑肥作物利用ならゼロ)。
一旦、飼い始めたら(意識を未来側に)
 満開のブルーベリー(写真右)は、植え付け時から4年間ほど大量の木材チップを、土に混ぜずに表面施用。雑草も適度な期間で刈り、表面に敷いています。
満開のブルーベリー(写真右)は、植え付け時から4年間ほど大量の木材チップを、土に混ぜずに表面施用。雑草も適度な期間で刈り、表面に敷いています。十分な餌を与えているため、イネ科(画像の左側1/3の濃い緑)の雑草が、ほぼなくなり、スギナ(右側2/3の株元を拡大した画像)も僅かに残るだけ。土壌改良が順調に進んでいることを、植物相(雑草)が如実に示しています。
現時点(結果)では、文句なしの土壌状態。しかし、ここ2年間は何も入れていないとのこと。チップは、ほぼ分解し終わり、このままだと1〜2年後には餌不足に陥ります。
木質資材の表面施用では分解が遅く、餌として有効化するのは投入の翌年以降です。幸いに、未投入の期間が使用資材の分解期間内ぎりぎりと思われ、今すぐ投入を再開すれば、何とか餌切れを起こさずに済みそうです。
このような表面施用では、投入有機物量(厚さ)により分解期間が変わります。敷く厚さにより投入間隔を調節します。土に混ぜた場合は量の多少に関わらず、食べ終わる迄の期間=分解期間は同じ。資材の分解速度に合わせ、一定間隔で与え続けます。
もちろん、生きものを飼うのですから、作物の有無(作付け)と関係なく餌は必要。一旦、飼い始めたら最後まで飼う。それが生きものを飼うということ。飼育者として、基本中の基本です。
結果=過去を見ていてはダメ。先を見る。意識を常に、未来側に置くことが炭素循環農法=自然農法の鉄則。これができていない内は、自然農法をやっているとは言えません。「やっている」と「できちゃった」は違います。
不味い(発酵成分不足)
 餌不足の症状は、見かけや収量だけではありません。作物の味や食感、内部品質などに、その影響が顕著に現れます。
餌不足の症状は、見かけや収量だけではありません。作物の味や食感、内部品質などに、その影響が顕著に現れます。
食感:
作物の味を正確に知るためには、一番不味いところを一番不味い状態(食べ方)で確かめる。また食味=味ではない。味+食感+温度や水分など総合的なものが食味。特にコメは要注意、食感に誤魔化されないようミキサーでドロドロにしてから味だけをみる。
作物の味を正確に知るためには、一番不味いところを一番不味い状態(食べ方)で確かめる。また食味=味ではない。味+食感+温度や水分など総合的なものが食味。特にコメは要注意、食感に誤魔化されないようミキサーでドロドロにしてから味だけをみる。
写真は、あまりの生育不良に耐えかねて?、葉面施肥をしたホウレン草の試験結果です。
・ 無施肥葉面施肥3回で辛うじて慣行並みの成育になったものの・・・。栽培者家族の評価順位と、その意味は、
・ 液肥の葉面散布1回
・ 同3回
1番 1回施肥: 不味い味も微量なら・・・。食感を除いて、味を決める代表的な要素は5つ。美味さは、糖成分、発酵成分。不味い味は、腐敗成分、硝酸成分やシュウ酸、農薬成分。これに資材(美味い=醗酵物、不味い=畜糞堆肥など)の風味が、そのまま作物に移行、プラスされます。
(僅かな硝酸によるアク。硝酸があるとシュウ酸なども増加)
2番 無施肥 : 美味くない。
(味が無い=美味しさも不味さもない)
3番 3回施肥: しっかり不味い。
(アクが強い)
このようなことを知らないと、葉面散布1回を「味が無いよりはマシ」と、アクを“うま味”と感じてしまいます。各地で実際に試食した物も同様な傾向です。
一番多いのは、自然猿真似農法からの転換や炭素循環農法に転換後3年以上経過。「2番」のような味がなく貧弱で、馬もまたいで通る?硬い野菜。無施肥に転換すれば不完全ながら、不味い成分はある程度減ります。しかし、餌不足や断食農法など栄養失調状態の作物は、美味しい成分が殆ど無いため「不味い!!!」のです。
次が「1番」のような、有機堆肥農法からの転換あるいは餌不足のため、浄化=生物化が不十分で僅かな腐敗味と硝酸味の「微不味+馬またぎ?」。
残りの極少数が、浄化度・発酵度もまあまあ。ただ転換初期のため時間(浄化期間)不足。かなり美味しいが「い抜き」の、惜しい味。
更に、全農推奨=典型的な有機堆肥栽培からの転換で、堆肥+腐敗+硝酸+発酵成分の「全濃味」。慣行施肥栽培からの転換初期で評価の対象外なども。さすがに(当たり前ですが)「3番」は、この試験例を除き皆無。
甘くなるのは光合成が盛んになり、大量にできたデンプンを糖に変え移動=エネルギー(糖)代謝が活性化するからです。同時にアミノ酸やビタミン類の産生・代謝も活性化します。
極端な低養分状態では、十分な光合成もできず糖の活性度が落ち、糖度が下がり内部品質も悪化し成長が遅れます。そして、成長に長期間を要すると作物全体が繊維化。硬くなり野生化、馬も跨いで通る?(笑)というわけです。馬跨ぎを本物と勘違いしないで下さい。
発酵成分の量は、餌の量に比例。餌が大量にあれば養分量が増えると同時に発酵成分の量も増え、成長が早く見かけも立派。甘くて柔く、発酵味の濃い。人に美味しくて、虫には食えない、健康な作物になります。
ある会場で「土作りは“糠みそ”と同じですね」という感想。全くその通り。それなりの時間をかけ十分発酵させなければ、美味しい糠みそ漬けができないのと同じです。
作物によっては・・・(餌さえ増やせば)
 写真のネギの内部品質は慣行栽培以上。収量では慣行並み。しかし、葉色が薄く先端が少し枯死。見かけでは少し劣ります。一般的な葉野菜なら、ほぼ十分な餌の量ですがネギでは、まだまだ不足です。
写真のネギの内部品質は慣行栽培以上。収量では慣行並み。しかし、葉色が薄く先端が少し枯死。見かけでは少し劣ります。一般的な葉野菜なら、ほぼ十分な餌の量ですがネギでは、まだまだ不足です。ネギ科など根が浅いものでは、他の野菜より養分濃度を高くしなければなりません。この状態なら餌を増やすだけで、全ての点で短期間の内に慣行栽培を超えることができます。
あくまでも、転換初期は葉野菜のみの栽培が基本。しかし、多少の工夫で栽培可能な作物が増えます。たとえ転換初期でも大量の炭素資材を極浅く混ぜ、更に炭素資材で厚くマルチをすればネギ類でも可。
表層に養分を集中させ、深部の未浄化部分を使わなくても済む。寒さに強く土地の有効利用が可能などの利点もあります。
転換初期は葉野菜:
地上部に対し根量が多く栽培期間が短い。その根を枯らし、微生物の餌にして土壌深部を耕す。作付け毎、炭素資材を混入でき投入量、回数を増やせる。転換時の虫食い現象などによる経済的損失を最小限に抑えられる。特別な栽培技術・知識を必要としない。故に農業初心者でも簡単に栽培できる。
地上部に対し根量が多く栽培期間が短い。その根を枯らし、微生物の餌にして土壌深部を耕す。作付け毎、炭素資材を混入でき投入量、回数を増やせる。転換時の虫食い現象などによる経済的損失を最小限に抑えられる。特別な栽培技術・知識を必要としない。故に農業初心者でも簡単に栽培できる。
 写真(右)はネギと同じ畑。生のチップが大量に入手可能なため、発酵処理した物を浅く混ぜ、更に植付け後、同じ資材でマルチしたジャガイモ畑です。これでも、特に問題はありませんが少々餌不足。既に土はきれい。思いっきり投入量を増やしても大丈夫です。
写真(右)はネギと同じ畑。生のチップが大量に入手可能なため、発酵処理した物を浅く混ぜ、更に植付け後、同じ資材でマルチしたジャガイモ畑です。これでも、特に問題はありませんが少々餌不足。既に土はきれい。思いっきり投入量を増やしても大丈夫です。何も加えずに堆積して発酵・発熱する様なものなら、無処理でも土の中で容易に発酵します。針葉樹でない限り、生のまま発酵処理せず未処理で投入した方が、より簡単・確実で省力・効果的です。
発酵・発熱する様なもの:
竹(イネ科で雑草の兄貴分?)や照葉樹、剪定枝(若枝)などは適度にC/N比が高く腐敗せず、しかも発酵に必要な糖分、窒素分なども適度に含まれている。
逆に、腐敗しやすい物を枯らすのは、これらの成分(特に窒素)をある程度分解させ飛ばすため。
針葉樹でない限り:
原始的な植物ほど(シダ、ソテツ、イチョウなど)菌類との共生関係が希薄。シダ植物の次に現れたヒノキ科(杉、檜)はフェルギノール、スギオール、ヒノキチオールなどの抗菌性物質を作る。外生菌根菌を作らず、菌類との共生関係が弱い。
ヒノキ科:
1属当たり、1〜数種と種類が少なく分布域も狭い、絶滅危惧種に近い?グループ(イトスギ属、ビャクシン属を除く。スギ科を分ける事もある)。
竹(イネ科で雑草の兄貴分?)や照葉樹、剪定枝(若枝)などは適度にC/N比が高く腐敗せず、しかも発酵に必要な糖分、窒素分なども適度に含まれている。
逆に、腐敗しやすい物を枯らすのは、これらの成分(特に窒素)をある程度分解させ飛ばすため。
針葉樹でない限り:
原始的な植物ほど(シダ、ソテツ、イチョウなど)菌類との共生関係が希薄。シダ植物の次に現れたヒノキ科(杉、檜)はフェルギノール、スギオール、ヒノキチオールなどの抗菌性物質を作る。外生菌根菌を作らず、菌類との共生関係が弱い。
ヒノキ科:
1属当たり、1〜数種と種類が少なく分布域も狭い、絶滅危惧種に近い?グループ(イトスギ属、ビャクシン属を除く。スギ科を分ける事もある)。
針葉樹の発酵処理はキノコの培地化堆積し3ヶ月前後、放置するだけ。急ぐ場合は堆積・切り返し(1〜2回)=短期高温発酵、一ヶ月で使えます。マルチ(表面に敷く)なら無処理で構いません。単純が基本、余計なことを考え無駄な手を加えれば複雑(人)農法です。
そして直ぐ使う。処理後やむを得ず長期間(1ヶ月以上)保存する場合は、拡げて水分を飛ばし発酵を止めておきます。写真のチップは堆積・発酵処理後かなりの時間が経過していますが内部温度は56度。木質部の分解が進み無駄に消耗している証拠です。
分解が進み無駄に消耗:
最初は比較的短時間で有害成分などが分解。次に糸状菌により木質部(セルロースやセミセルロース、リグニンなど)が分解される。どちらの分解作用も発熱するが一旦、高温になり熱が下がってくると糸状菌が働き始める。この時が使用適期。
最初は比較的短時間で有害成分などが分解。次に糸状菌により木質部(セルロースやセミセルロース、リグニンなど)が分解される。どちらの分解作用も発熱するが一旦、高温になり熱が下がってくると糸状菌が働き始める。この時が使用適期。
場の活用(マイナス要因を活かす)
 虫や菌を生かすためには、たとえ人為的な結果としてのマイナス要因(耕地化、温暖化、高炭素社会など)でも活かさなければなりません。特に転換時にはその場の気候・土壌などの自然条件、土の経歴や経済的な立地条件などの人為的な環境を見極め、マイナス要因を逆手にとりプラスに転換。場(環境)を含めて全てを活(生)かすのが自然農法です。
虫や菌を生かすためには、たとえ人為的な結果としてのマイナス要因(耕地化、温暖化、高炭素社会など)でも活かさなければなりません。特に転換時にはその場の気候・土壌などの自然条件、土の経歴や経済的な立地条件などの人為的な環境を見極め、マイナス要因を逆手にとりプラスに転換。場(環境)を含めて全てを活(生)かすのが自然農法です。写真(拡大=webアルバム)は、海浜地帯の低湿地におけるピーマンのハウス栽培。一見悪条件に思えますが逆に捉えれば、地下水位が高く水が豊富。降雨の影響を直接受けないハウスは乾湿の制御が容易。砂質土壌は水を抜きやすい、緩衝能が小さく土壌改良対策に対し土が敏感に反応する。など仕組みを理解すれば、むしろ有利な条件です。
初回訪問時(2009年3月)には、潅水チューブの周りには緑の藻、窒素不足で黄色い苗。これは表層が過湿状態で、根が水を求め下に伸びず根域が小さいためです。また、過灌水により土壌中が酸欠状態で投入資材の分解が遅いのも一因。同様の理由から軽度の腐敗もあり、ミミズやダンゴムシ、オケラの天国になっていることが、それを証明しています。
餌は十分入れたとのこと「極力水を減らして下さい」とアドバイス。そして2ヶ月後(写真)。藻も虫も消え雑草も芽を切ることができません(周辺農家から除草剤を使ったのかと聞かれるほど)。根は水を求め下に向かって伸び、豊富な地下水層に達し天然水耕状態。乾燥の激しいハウスでも、もう潅水の必要はありません。
表層が乾燥した結果、通気性が良くなり糸状菌が活性化。炭素資材の分解が順調に進み、微生物相が豊になり窒素固定が十分行われ、根域も拡大していることが葉色に現れています。もちろん腐敗も止まり、虫食いは全く見られません。
特に、乾燥しやすいハウス栽培では生育初期から水を控え、できるだけ早く下層まで根を伸ばすことが重要。そのためには表層は砂漠マルチ?状態「濡らさない、心土を土を乾かさない」が鉄則です。
砂漠マルチ?:
表層に十分団粒化し乾燥した数cmの層ができると、土粒子の隙間が毛細管現象が起きないほど大きくなり、下層から上がってきた水がそれ以上、上には行かなくなる。究極の土耕マルチ(耕した土で下の土をマルチ)。通常の土壌を乾かすと地割れができ、心土の深くまで乾いて水不足を来す。
実践2の圃場で、ペットボトルの底を切り落とし乾燥した表土を詰め、水盤上に立てた試験では 1cm/時間 上昇。同様に、その下の湿った心土を詰めたものでは 10cm/時間 上昇。という結果がでた。
直射日光の強い亜熱帯の乾季でも、灌水不要になるのは硬盤層が消えれば、土壌深部からは速やかに水が上がってくるが、乾燥した表土がマルチの役目をして水を逃がさないからである。また、蒸散量が僅かなため、表層の塩類蓄積も起きない。
表層に十分団粒化し乾燥した数cmの層ができると、土粒子の隙間が毛細管現象が起きないほど大きくなり、下層から上がってきた水がそれ以上、上には行かなくなる。究極の土耕マルチ(耕した土で下の土をマルチ)。通常の土壌を乾かすと地割れができ、心土の深くまで乾いて水不足を来す。
実践2の圃場で、ペットボトルの底を切り落とし乾燥した表土を詰め、水盤上に立てた試験では 1cm/時間 上昇。同様に、その下の湿った心土を詰めたものでは 10cm/時間 上昇。という結果がでた。
直射日光の強い亜熱帯の乾季でも、灌水不要になるのは硬盤層が消えれば、土壌深部からは速やかに水が上がってくるが、乾燥した表土がマルチの役目をして水を逃がさないからである。また、蒸散量が僅かなため、表層の塩類蓄積も起きない。
ここではミスト装置が既に設置済み。土壌潅水より、ミストによるハウス内の加湿が有利。施肥栽培の作物(虫や菌の餌)と違い、濡らしたり湿度を上げたからといって病虫害は発生しません。
自然の日サイクルの温湿度や作物の生理に合わせ、昼は乾かし、朝夕は自然の霧や露が付いた状態を再現。噴霧量は雫の滴下で地表を濡らさない程度が目安です。
農業誌に載った、たった数ページの記事だけを頼りに始めて、短期間でここまで良くなるとは、さすがはプロ。農業専門誌の編集者の驚きに同感です。度胸の良さと勘の鋭さは、作物に対する確かな技術の裏打ちがあってこそでしょう。
選ばない(自在であれ)
 ここ(写真 詳細説明=webアルバム)はイチゴの専業農家。ほぼ無農薬(生育初期に短期間、漢方的防除資材を使用)。イチゴの無農薬栽培を目指し全国を歩き回るも手本は無し、自分でやるしかないとの結論。ここ(炭素循環農法)を知り転換、2年目です。この様子なら、来期(3年目)は完全無防除でしょう。
ここ(写真 詳細説明=webアルバム)はイチゴの専業農家。ほぼ無農薬(生育初期に短期間、漢方的防除資材を使用)。イチゴの無農薬栽培を目指し全国を歩き回るも手本は無し、自分でやるしかないとの結論。ここ(炭素循環農法)を知り転換、2年目です。この様子なら、来期(3年目)は完全無防除でしょう。ここでの特筆すべきことは「入手可能な物は手当たり次第(笑)何でも使う」です。幸い近くに大手の食品加工会社があり、食品加工の残滓(肉や魚、海藻、発酵食品などのミネラル豊富な窒素源)が入手できます。使い方は基本に則り、高炭素資材と混ぜて何でも発酵。発酵状態を臭いで判断して(良い臭い、美味しそうな臭いならOK)、混合比や使用時期などを決めます。
ここに限らず、それなりの成果を上げているところは特定品目の専業です。共通点は、いきなり転換。餌もしっかり入れる。化学肥料や農薬も思いっきり使った経験があるなど、とにかく「やることが半端じゃない」。
慣行農法と正反対ですから、半端では成果が上がりません。ごちゃごちゃ能書き(今、流行の?)並べて、色々やっている者ほど成果を上げていません。
その場の環境に合わせる=自然の基準に合わせる。使用資材についても同じ。その場で容易に調達可能な物に限る(合わせる)のが当然。何もなければ雑草&作物残滓ですが利用可能な物は、何でも使ってこそ自然(に従う)農法というものです。
百、千ha単位の広大な農地では緑肥作物利用以外は無理があります。しかし、少なくとも日本では炭素資材に事欠くことはない筈。廃棄物扱いされ処理に困っている物などがあれば、それを使わないのは反自然です。キノコ廃菌床(教材)は、あればの話、なくても別に困りません。
混ぜない(過ぎたるは・・・)
秋から冬は好気性で低温に強い菌類(糸状菌)が活性化し、土壌中の酸素消費量=餌の消費量が増えます。降雨が少なく土壌水分が減った分、気相が増えるためと低温に弱い細菌類(バクテリア)に邪魔をされない?、などの理由が考えられます。特に、この時期の不用意な耕起は思わぬ結果を招きます。秋起こし稲ワラ混入後、更に腐敗成分を飛ばそうと、冬の間に2回耕起した水稲の例では、日本の標準反収8.8俵の半分以下。
高炭素資材=餌を何も投入せずに、秋から冬にかけて除草代わりに3回ほど耕起した畑では収穫ゼロ(殆ど成育せず)。
耕起した結果、酸素の供給過剰となり有機物の分解が進み過ぎ消耗。「過ぎたるは・・・」です。二例とも気相が増える時季に耕起したため、より顕著な結果になりました。
逆の好結果の水稲例(炭素循環農法は知らないが、もちろん無施肥)では、代かき時の作業集中を避け秋に分散(ワラ+秋起こし)&中干しナシ、通常の水管理(水を切らさない=水が残っている内に入れる)。肥抜き、手抜きの結果は11俵/反。しかも、3年で無防除・無除草剤。理に叶ってさえいれば何も知らず、特に苦労や努力などをしなくても、全ての点で慣行以上が当たり前。それが自然なのです。
ワラ:
貴重な餌(炭素源=エネルギー源)。この一例だけで「ワラをバイオ燃料に・・・」が如何に馬鹿げた発想かが分かろうというもの。彼ら(学者や政治家)には、何も見えてはいない。分かっちゃいない。どのような技術開発でも意味を考えてからやることである。
貴重な餌(炭素源=エネルギー源)。この一例だけで「ワラをバイオ燃料に・・・」が如何に馬鹿げた発想かが分かろうというもの。彼ら(学者や政治家)には、何も見えてはいない。分かっちゃいない。どのような技術開発でも意味を考えてからやることである。
時季を問わず、餌入れ以外の耕起は有害です。土壌改良は、表層での有機物分解(養分化・団粒化)→根が深く入る→枯れた根を分解(深部の団粒化)。これの繰り返し。冬期に作付けできない地域では、根を枯らして土壌深部への有機物供給もできません。
植物と微生物の連携がないと、餌の消費の割には土壌改良は進みません。また、作物や雑草がない時季は養分化の必要もなし。春先までに、ゆっくりと分解させ地力(バイオマス)を温存した方が無駄がありません。
作物ができない冬は何もせず、有機物を無駄に消耗させないことです。また、思いの外、餌を食べるということを念頭において、作付けをしない冬期にも餌不足を起こさないよう、秋にたっぷり与え春に備えます。 更に、必要以上に空気が入らないような対策も有効です。餌を少し深めに入れる。土を細かく砕いて隙間を減らす。鎮圧する。マルチ。など乾燥し過ぎないようにします。
混ぜる(複利で稼ぐ)
 写真(左)は大量の廃菌床と高炭素有機物が敷かれ、見た目は如何にも「やっています」の状態。何となく精神衛生上は良さそうですが?・・・。イソップ寓話の「狐と鶴のご馳走」です。
写真(左)は大量の廃菌床と高炭素有機物が敷かれ、見た目は如何にも「やっています」の状態。何となく精神衛生上は良さそうですが?・・・。イソップ寓話の「狐と鶴のご馳走」です。この与え方では、接地面だけしか食べられず、土に混ぜた場合に比べ土壌改良に3倍以上の時間を要します。単に、ご馳走を与えればよいわけではありません。食べられる状態で与えることが肝要です。
相手の立場(微生物の側=自然)に立って物事を捉える。自然が基点。故に自然農法。この基本中の基本を理解せず自然農法は語れません。
世界で最初の自然農法(バイオダイナミック農法)の提唱者ルドルフ・シュタイナーが説いたのはこのこと(捉え方:向こうから観る=意識の地動説)なのです。彼の説いた詳細部分は、その時代に合わせた説明をしただけのことです。
詳細部分は:
日本人にとっては殆ど理解不能な星座の運行を元にした、ややこしい暦やオカルトチックなおまじない(調合剤=意識世界の仕組みの応用)などは知らなくても特に支障はない。日本民族は星が見えない山の民、自然に同化することで身の保全を計ってきた。欧米民族は草原の民、身を隠すことができず対峙するしかなかった。日本でBD農法が流行らないのも、一神教になじめないのも(日本人に真の一神教徒がいるとは思えない)、これが起因と考えられる。そもそも捉え方が違うものを、そのまま使うことには無理がある。
日本人にとっては殆ど理解不能な星座の運行を元にした、ややこしい暦やオカルトチックなおまじない(調合剤=意識世界の仕組みの応用)などは知らなくても特に支障はない。日本民族は星が見えない山の民、自然に同化することで身の保全を計ってきた。欧米民族は草原の民、身を隠すことができず対峙するしかなかった。日本でBD農法が流行らないのも、一神教になじめないのも(日本人に真の一神教徒がいるとは思えない)、これが起因と考えられる。そもそも捉え方が違うものを、そのまま使うことには無理がある。
 当然ながらご馳走に対する返礼(写真右)はこうなります。虫や菌のご馳走ではあっても、人のご馳走ではありません。順調なら転換後、半年から一年でこの状態になります。しかし既に3年経過していて、未だこのような虫食い現象が現れるのは浄化速度が極端に遅い証拠。施用量(写真上)の割には、土壌改良が進んでいないということです。
当然ながらご馳走に対する返礼(写真右)はこうなります。虫や菌のご馳走ではあっても、人のご馳走ではありません。順調なら転換後、半年から一年でこの状態になります。しかし既に3年経過していて、未だこのような虫食い現象が現れるのは浄化速度が極端に遅い証拠。施用量(写真上)の割には、土壌改良が進んでいないということです。資材の質や量には問題ありません。与え方が不適切なだけです。果樹などを除き、必要な餌の全量は必ず土に混ぜます。混ぜた分だけが餌です。
表面に敷いた分は、あくまでもポリフィルムなどの代用。直ぐ食べられない状態の物は餌ではありません。餌とは全く別の物(マルチ資材)と考えて下さい。
果樹などを除き:
基本的に耕起しない果樹園などでは表面施用である。しかし、作物残滓や草などのように易分解性成分が雨で流されたり大気中に逃げるということが少ない。同じ表面施用でも木材チップ(無処理)の場合は、極端に炭素比が高く超難分解性の木材は、糸状菌(キノコ菌)により接地面から徐々に分解され、その菌糸はチップ内だけでなく同時に地中にも伸び(一つの胞子から伸びた菌糸はどんなに広がっても一個体)養分の移動を行う。キノコによる放射性物質の生物濃縮もこの性質が起因。
基本的に耕起しない果樹園などでは表面施用である。しかし、作物残滓や草などのように易分解性成分が雨で流されたり大気中に逃げるということが少ない。同じ表面施用でも木材チップ(無処理)の場合は、極端に炭素比が高く超難分解性の木材は、糸状菌(キノコ菌)により接地面から徐々に分解され、その菌糸はチップ内だけでなく同時に地中にも伸び(一つの胞子から伸びた菌糸はどんなに広がっても一個体)養分の移動を行う。キノコによる放射性物質の生物濃縮もこの性質が起因。
利子を元金に繰り入れ、複利で稼ぐのが循環農法。一定期間内に、どれだけの量の餌を何回、表層の微生物に食べさせたか。同様に土壌深部の微生物に作物や雑草の枯れた根を食べさせたかで勝負が決まります。
もちろん生きた根からも微生物に養分は供給されます(土を休ませない方が良い理由の一つ)。できるだけ早く元利合計を増やす工夫が必要。特に初期は元金の追加と利子の繰り入れ回数を増やすこと、非常に高利ですから運用の仕方次第で何倍もの差がつきます。
マメ科は土を痛める(連作不可)
 このまま(写真左:ヘアリーベッチ)代かきすれば確実に腐敗します。水田での緑肥栽培は、田植え迄の時間的制約や緑肥の収量のコントロールも難しく(穫れすぎると過剰施肥になる)手間もかかります。
このまま(写真左:ヘアリーベッチ)代かきすれば確実に腐敗します。水田での緑肥栽培は、田植え迄の時間的制約や緑肥の収量のコントロールも難しく(穫れすぎると過剰施肥になる)手間もかかります。また、代かき時(嫌気状態)の腐敗分解による雑草抑制効果もありますが、逆に腐敗を抑えて無除草剤にした方が温室効果ガスのメタン(二酸化炭素の20-30倍)や硫化水素なども出ず、環境負荷を低減できます。
蓮華草の咲く風景などが見られないのは残念ですが、危険度が高く景観以外「良いとこなし」。割に合わない?技術(所詮は施肥栽培の技術)。反自然にならないためには、マイナス要因のない(少ない)ものを選ぶのが基本です。
 ゲンゲ(レンゲ)、ヘアリーベッチ、カラスノエンドウ(雑草)、何れもマメ科(写真右)。ゲンゲやヘアリーベッチで100kgN/haほどの窒素固定能力があると言われ、これが災いし鋤込めば腐敗します。
ゲンゲ(レンゲ)、ヘアリーベッチ、カラスノエンドウ(雑草)、何れもマメ科(写真右)。ゲンゲやヘアリーベッチで100kgN/haほどの窒素固定能力があると言われ、これが災いし鋤込めば腐敗します。
鋤込めば腐敗:
この条件下で腐敗させないために、土や水(微生物)に必要なものは炭素。その必要全炭素量は4tC/ha(乾燥状態の炭素資材で10t)。これはC/N比40まで上げるのに必要な最低量。緑肥作物自体にその半量がある(C/N比20)と仮定すると、高炭素資材を乾燥重量で5t(木質系)〜10t(ワラや籾殻)/ha(発酵処理直後ならその2〜3倍)ほど補給すればよい。
この条件下で腐敗させないために、土や水(微生物)に必要なものは炭素。その必要全炭素量は4tC/ha(乾燥状態の炭素資材で10t)。これはC/N比40まで上げるのに必要な最低量。緑肥作物自体にその半量がある(C/N比20)と仮定すると、高炭素資材を乾燥重量で5t(木質系)〜10t(ワラや籾殻)/ha(発酵処理直後ならその2〜3倍)ほど補給すればよい。
これらの緑肥作物は通常水田で栽培されます。先ず刈ってから数日干し(半生状態)、高炭素資材(発酵処理済み)を追加。極浅く耕起(混ぜ込み)。その後、最低でも6週間ほど好気状態で発酵させてから代かき。熱帯の二毛作田ではワラや稲株だけをこの方法で処理し次の田植えをしています。
寒い日本では実際には時間的に無理。水稲の緑肥利用はお奨めできません。「稲ワラ&手抜き」だけでも、慣行施肥栽培より遙かに高収量です。先ずそちらが先。更なる増収を狙うなら、高炭素資材の追加だけに留めた方が無難。
また、空いた期間を無駄にしたくなければ別の作物を裏作として栽培すればよいのです。尤も、残滓処理にはマメ科緑肥と同様な注意が必要。畑と違って代かき時には貧酸素状態になるため、腐敗防止処理をしていない“生の物”を絶対に鋤込んではいけません。
マメ科緑肥は畑でも同じ。相対的窒素過剰になり腐敗を招き土を痛めます。極端な痩せ地でのイネ科緑肥作物との混植以外はお奨めできません。同じ理由からマメ科作物だけは連作不可。マメ科の後には、炭素固定能力が高く窒素消費の多い作物を選ぶのが最良。特にイネ科作物が向いています。
以下準備中
| 4 | − | 9 | 2 | |
| | | | | |||
| 3 | − | 5 | − | 7 |
| | | | | |||
| 8 | 1 | − | 6 |